新しい「育成就労」制度の下で日本は外国人労働者に定着してもらえる国になれるのか 
京都大学大学院文学研究科准教授(国際連携文化越境専攻)
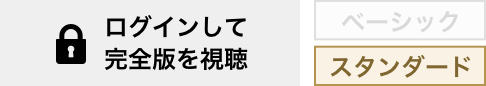


| 完全版視聴期間 |
(期限はありません) |
|---|
1965年兵庫県生まれ。91年京都大学法学部卒業。92年司法試験合格。95年大阪弁護士会登録。中道法律事務所を経て2003年あかり法律事務所を開設。生活保護問題対策全国会議事務局長を兼務。共著に『これがホントの生活保護改革 「生活保護法」から「生活保障法」へ』など。
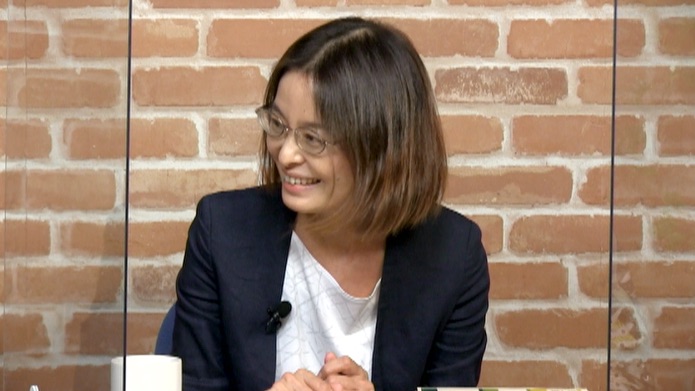
画期的な判決だった。
2月22日、大阪地裁は、2013年から段階的に行われた生活保護基準引き下げについて、厚生労働省の裁量権の逸脱・濫用であり、「健康で文化的な生活水準を維持することができる」とする生活保護法に反するという判決を下した。同様の訴訟が全国29都道府県、1000人を超える原告によって提訴されており、それらの裁判の行方も注目される。
1月の参議院予算委員会で、コロナ禍で生活困窮者が増えていることについての考えを問われた菅首相は、「最終的には生活保護がある」と豪語した。しかし、利用する上で数々のハードルが設けられている上に、金額的にも決して十分とはいえない現行の生活保護制度は、首相が胸を張るような憲法が保障する「最終的」な生活防衛手段とはほど遠いものとなっている。
しかも、ただでさえ問題が多く不十分な生活保護費が、年々削減されている。2013年の削減で、平均6,5%、最大で10%、総額で670億円削減された。デフレ調整という理由での削減だったが、それは生活保護基準を検討する専門家の部会で議論もされないまま、厚労省が独自に用いた消費者物価指数による計算に基づいて断行されていた。この方法自体が恣意的とも取れるものであり、大阪地裁によって「最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があり」違法と判断されたのだった。
この引き下げについて、生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は、行政が政治によって歪められたケースだと強く疑問を呈す。お笑い芸人の親族の生活保護受給が明らかになったことが引き金となり、生活保護バッシングが起きたのが2012年。その年の12月の総選挙で当時野党だった自民党は、生活保護給付水準の10%削減を公約に掲げていた。そしてその選挙で自民党は政権に返り咲き、公約どおり生活保護費の引き下げを断行したのだ。
生活保護費は住民税非課税枠や国民健康保険料など、他のさまざまな社会保障制度の基準とも連動する。生活保護費がナショナルミニマム(国民生活で保障されるべき最低水準)の指標となっているからだ。その指標が生活実態に則した根拠のないまま、政権公約に基づく机上の数字合わせだけで引き下げられていたとすれば、それは非常に大きな問題だ。公約通り生活保護費が引き下げられた裏でどのような政治力学が働いていたのかは、厳しく検証される必要がある。
生活保護バッシングがさらに問題なのは、国民のなかに生活保護に対する忌避感が広がってしまったことだ。日本の場合、生活保護の捕捉率がそもそも2割程度しかないことはこれまでもたびたび指摘されてきた。さらにその上で今、特に問題となっているのが、そもそも法律には要件とはされていない「扶養照会」が、実際には広く行われていることだ。扶養照会とは、自治体職員が親族などにその人物を扶養する余裕はないのかなどを質問する制度だが、元々、日本の民法上の扶養義務の範囲は諸外国に比べて極めて広いため、多くの生活困窮者が親族に迷惑がかかることや、親族に自分が生活保護を申請していることを知られることを嫌がって、生活保護申請を諦めるケースが多いとされている。現実には旧来型の家族像や親族関係は形骸化しているにもかかわらず、生活保護を受給する際に祖父や祖母、兄弟姉妹にまで扶養照会が行われることにどれだけの意味があるのか。それは生活保護受給を断念させるための、単なる嫌がらせなのではないか、と小久保氏は訝る。
新型コロナ禍で生活困窮に陥る人が急増し、相談件数もうなぎ登りだ。感染流行が長引くことで、現状は貸し付けなどで何とか凌いでいる人たちが今後さらに苦境に追い込まれる可能性もある。それでも生活困窮者の相談の現場では「生活保護だけは受けたくない」という相談者が多いという。昨年末から厚労省はホームページ上に「生活保護は国民の権利です」との文言を載せ、生活保護の利用を形の上では勧めているが、浸透しているとはとても言えない。
権利としての生活保護を定着させるためには、「生活保護」ではなく「生活保障」という新たな発想が必要ではないか主張する小久保氏に、ジャーナリストの迫田朋子が聞いた。