五輪談合事件に見る、捜査能力の劣化で人質司法に頼らざるをえない特捜検察の断末魔 
弁護士
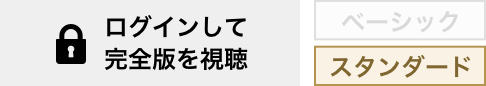


| 完全版視聴期間 |
(期限はありません) |
|---|
相次ぐ冤罪や検察不祥事を受けて刑事司法改革を議論している法制審議会の特別部会が、司法取引の導入を決定する見通しだというが、可視化や証拠の開示が不十分なまま司法取引が導入されれば、さらなる冤罪の温床となることは目に見えている。今、日本の刑事司法制度に求められる改革とは明らかに逆行する施策と言わねばならない。
そもそもこの特別部会は、冤罪の原因となっている人質司法や取り調べの可視化、検察の証拠開示を改革することが主眼になるはずだった。ところが3年間にわたる議論の末、出てきたものは明らかに不十分な可視化策と証拠開示基準だった。現在特別部会が検討している可視化策は裁判員裁判の対象事件のみを可視化の対象とするもので、刑事事件全体の2%程度しか可視化されないことになる。
また、証拠開示についても、証拠のリストのみを公表すればいいことしている。刑事事件を担当する弁護士たちの話では、証拠につけられた文書タイトルから証拠の中身を判断することは不可能なので、仮にリストを受け取ってもまったく証拠が開示されたことにはならないと言う。
しかも、その一方で、特別部会は盗聴法の強化などの捜査権限の強化だけはしっかりと謳われるなど、本末転倒な報告が相次いで出されていた。
特別部会は6月23日の会合で、更にその上に、新たな捜査権限の拡大策として、「司法取引」の導入を議論し始めたという。司法取引は事件の容疑者が捜査に協力する見返りに刑が軽減されたり起訴が見送られたりする制度だが、これが新たに捜査権限に加わることで、既に権力が集中しすぎていると批判される検察が、更に新たな武器を手にすることになる。
司法取引には大きく分けて、(1)容疑者や被告が共犯者など他人の犯罪を解明するために協力することの見返りに、検察官が起訴を見送ることができる「協議・合意制度」、(2)自分の犯罪を認めれば刑を軽くすることができる「刑の減軽制度」、(3)事故などの原因究明のために、容疑者になり得る証人にあらかじめ免責を約束したり、証言を証人の不利益な証拠にできないとの条件を付けることができる「刑事免責制度」の3類型がある。(2)は裁判コストの削減、(3)は事故原因究明を優先するための設けられた制度だが、(1)は明らかに検察の捜査権限を強化するためのものだ。
欧米では既に何らかの司法取引制度が導入されている国が多いが、いずれの制度も取り調べが可視化されておらず、検察の証拠開示が行われていない日本でこれが導入されれば、更に冤罪の温床と化す恐れがある。検察側が実際には存在しない証拠があるかのように被疑者を騙し、司法取引を持ちかけて自白を取り付けることが可能になるからだ。
いずれにしても今回の特別部会の提言に沿って可視化が行われた場合、可視化の対象事件は全事件の2%強にとどまる見通しだ。つまり、可視化されていない事件で、密室の取り調べの後の司法取引が可能になるということだ。
法制審議会の特別部会は痴漢冤罪事件を扱った映画「それでもボクはやってない」の監督の周防正行氏や証拠捏造による冤罪事件の被害者となった村木厚子厚労次官らの一部を除き、圧倒的多数を検察、警察、裁判所などの法曹関係者が占めている。例えは悪いが、泥棒に泥棒を捕まえるための制度設計を任せているのも同然だ。そのような会議から、本当の意味で刑事司法の健全化や正常化を推し進めるための手立てが提言されるはずがない。
国連拷問禁止委員会の場で「中世」とまで揶揄されてもなお、実効性のある改革よりも権益の拡大を優先している日本の刑事司法に未来はない。そもそもこのような委員会に刑事司法改革を任せている政治の責任も重大だ。
1989年にニューヨークで5人の黒人とヒスパニック系の少年が白人女性を強姦し重傷を負わせた所謂「セントラルパーク5」事件というものがある。当時14歳から16歳の少年だった被告全員が7年から13年の服役を終えた後の2002年、突如として真犯人が現れ、少年たちはまったくの冤罪だったことが明らかになった。その事件でこのたび彼らを訴追したニューヨーク市と元少年らの間で和解が成立し、5人で合計して40億円の賠償金が支払われることになったという。概ね1人あたり1年につき1億円の補償額となる。
これも当時ニューヨーク市では取り調べが可視化されていなかったため、少年たちは苛酷な取り調べを受けた上に虚偽の自白を強要され、結果的に世紀の冤罪事件を作り出してしまった。しかも少年たちが自白をするシーンは繰り返しリハーサルを行った上でビデオ撮影され、それが裁判に証拠採用されている。現在の日本と同じ検察の都合のいい部分だけを録音・録画することが許される「部分可視化」の結末だ。
それから25年経った今、日本では今なお取り調べの可視化は実現していない。冤罪で17年半も不当に刑に服した菅家利和さんの国家賠償額は8000万円あまり、同じく冤罪で34年間不当な刑に服した免田栄さんの賠償額も9000万円あまりである。自分の人生の大切な時間を国家によって不当に奪われたことは無論お金で取り返しがつくものではないが、日本では検察や警察、そして裁判所にとって冤罪を起こしてしまった場合のリスクが、アメリカと比べて遙かに小さいこともまちがいない。
まだ遅くはない。特別部会には今からでも、どうすれば冤罪を防ぐことができるかを真剣に議論し、まずは少なくとも先進国として恥ずかしくない公正な刑事司法制度を確立してから、捜査権限の拡大や司法取引の議論をすべきだろう。
現行制度の元で司法取引を導入することのリスクなどについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。