五輪談合事件に見る、捜査能力の劣化で人質司法に頼らざるをえない特捜検察の断末魔 
弁護士
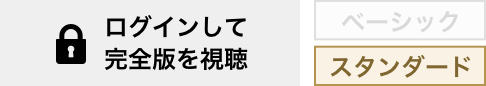


| 完全版視聴期間 |
(期限はありません) |
|---|
再審が決まった袴田事件の主任弁護人を務めた西嶋勝彦弁護士が11日会見し、長期間の勾留と苛酷な取り調べで被疑者を自白に追い込む「人質司法」や検察に都合の悪い証拠が開示されない現在の不公正な司法制度の下では冤罪事件の多発が避けられないとして、一度執行されてしまえば取り返しがつかなくなる死刑を継続することに疑問を呈した。
西嶋氏は「(袴田氏の自白が頼りになり)必然的に人質司法の典型として、捕まえて自白させて証拠の中心に据えようという構造が見えてくる」と語り、とても決定的な証拠とは言えない弱い証拠で袴田巌氏を逮捕し、拷問のような長時間にわたる苛酷な取り調べで自白に追い込んだ上で死刑判決に至った袴田事件の教訓を強調した。
一方、先進国の中では日本と並び数少ない死刑存置国のアメリカでも、死刑をめぐる新たな論争が起きている。死刑を禁じているEUの製薬会社が、死刑執行に使用される薬剤の輸出を拒み始めたために、アメリカでは薬物投与による死刑の執行に支障を来し始めているというのだ。実際に4月にはオクラホマ州で、新しい組み合わせの薬剤を使って死刑が執行されたが、薬の効果が不十分だったために死刑囚が苦しみ始め、途中で刑の執行を中止したものの、43分後に心臓麻痺が原因で死刑囚が死亡するという痛ましい事故まで発生している。
国連の場で「中世」とまで揶揄される刑事司法制度の改革が待ったなしであることは論を待たないが、そのような制度の下で死刑の執行を継続することの是非を含めて、刑事司法の深刻な問題は、もはや利害当事者が大多数を占める法制審議会の特別部会などには任せておける状況ではない。
ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が今週のマル激本編のテーマでもある倫理の問題とも絡めながら、日本の刑事司法制度が抱える問題や利益相反問題を議論した。