北方領土問題解決の千載一遇のチャンスを逃すな 
京都産業大学教授・元外務省欧亜局長
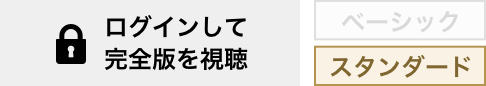


| 完全版視聴期間 |
(期限はありません) |
|---|

1945年長野県生まれ。68年東京大学教養学部教授。同年外務省入省。ソ連課長、条約局長、欧亜局長などを経て2002年退官。プリンストン大学研究員、カリフォルニア州立大学客員教授などを経て10年より現職。世界問題研究所長を兼務。博士(人文科学)。著書に『北方領土交渉秘録』、『返還交渉 沖縄・北方領土の「光と影」』など。

日露両国が1956年の日ソ共同宣言を基礎に、長年の懸案だった領土問題に終止符を打ち、平和条約締結に向けて動き出したようだ。
北方領土について長らく日本政府は、4島は日本固有の領土との立場を貫いてきたが、日本が4島を主張する限り、実効支配するロシア側を交渉のテーブルに着けることさえ難しい状況の中、遂に安倍首相が2島返還の受け入れを決断したとされている。
しかし、ことがそう簡単に進むかは不透明だ。
まず日本政府が冷戦下でアメリカ政府の意向もあり、北方領土や4島の一括返還しかあり得ないとの立場を貫き、その路線で世論の誘導を図ってきたため、2島返還での妥結を国民にどう説明するかという、国民感情の問題がある。これは自民党自身が積極的に、そして意図的に作ってきた世論でもあるため、その旗を降ろした場合の反発がどの程度のものになるかは予想がつかないところがある。
第二次大戦でのソ連軍の北方領土への侵攻がポツダム宣言受諾後だったことや、日本の千島の放棄を明記したサンフランシスコ講和条約にソ連が署名していないことなどから、国際法上はさまざまな議論の対象となってきた北方領土だが、ソ連、そしてロシアが70年以上にわたり4島を実効支配していることと、1956年の共同宣言では2島返還に傾いた日本政府がその後、一貫して4島の主権を主張していることは周知の通りだ。仮に両国の首脳が「やろう」と意気投合したところで、その溝は簡単には埋まりそうもない。
また、仮に共同宣言に立ち返ることで色丹島と歯舞群島における日本の主権が認められ、平和条約の締結が実現しても、共同宣言では引き渡しは「平和条約締結後」となっているだけだ。実際の引き渡しがいつになるかについての保証はない。
デリケートな交渉ごとなのでロシア側からは、「共同宣言には主権まで引き渡すとは書かれていない」とか「返還後、北方領土には米軍を駐留させないことを保証しろ」等々、いろいろなくせ弾が飛んできているようだが、今回のロシア側の攻勢の背後にある意図が今ひとつ不透明なことや、最後の任期を迎え後世に名を残す功績をあげたい安倍首相の焦りが透けて見えることなどから、性急な交渉に不安を覚える向きが多いのも事実だ。
2島をまず取り返した上で、択捉と国後では経済協力などのプラス・アルファを勝ち取るという「2島+α」説も、下手をすると2島が無条件で戻ってくるわけではない「2島-α」になりかねないと懸念する向きもある。
しかし、ソ連課長時代から北方領土の交渉に携わってきた元外務省欧亜局長の東郷和彦氏は、万難を排してでも、まず2島の返還で交渉を前に進めるべきだと主張する。長年、日ソ、日露の交渉に携わりながら、大きく隔たる両国の主張の間で、常に厚い壁にぶち当たってきた東郷氏は、プーチン大統領と安倍首相が平和条約締結に向けて領土交渉を前進させる意思を確認し合っている今の状態は、千載一遇のチャンスであり、またこれが最後のチャンスになるだろうと語る。
「これまで日本は(北方領土問題を解決する)チャンスが2度あったが、それをことごとく逃してきた。これが3度目の正直であり、最後のチャンスになると思う」と東郷氏は語る。
東郷氏が「最後のチャンス」を強調するのには理由がある。確かに北方領土は1855年に日露通好条約で日本の領有権が確認されてから、第二次大戦まで終結までの90年間は日本の支配下にあったが、その後70年以上もロシアが実効支配し、ロシア政府の施政下に置かれている。近年はロシア政府によるインフラ整備も進み、住民の生活環境は大幅に改善されてきている。また、北方領土には中国や韓国の資本が入ってきているが、領土問題を抱える日本は、政府が国民に北方領土への渡航自粛を求めていることもあり、完全に出遅れている状態だ。この状態が続けば、根室から目と鼻の先にある島々が返還されないばかりか、日本が全く関与できないまま発展を遂げていくことになると東郷氏は指摘する。
外交官時代、東郷氏は2島返還論を推進したことで、鈴木宗男氏や佐藤優氏らとともに世論や政府内からの指弾を受け、2002年に外務省を追われた。しかし、世論も政治状況も、当時とは大きく変わってきていると東郷氏は言う。
一貫して2島返還を主張してきた東郷氏に、2島返還論の是非や日本にとってどのようなリスクがあるかなどを、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。