NATOの拡大で変わる欧州の安全保障と日本が考えるべきこと 
東京大学大学院法学政治学研究科教授
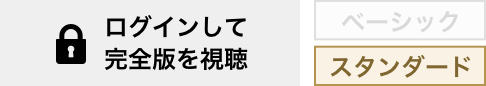



1966年東京都生まれ。89年北海道大学法学部卒業。92年ベルギー・ルーヴァン・カトリック大学修士課程修了。96年英オックスフォード大学政治学博士課程修了。政治学博士。米ハーバード法科大学院研究員、仏パリ政治学院客員教授、北海道大学助教授などを経て、2006年より現職。著書に『統合の終焉 EUの実像と論理』、編著に『グローバル・コモンズ』など。
イギリスの国民投票によるEU離脱は、世界の民主主義の在り方を根底から変えるかもしれない。
イギリスは6月23日に行われた国民投票で、EU(欧州連合)からの離脱を選んだ。予想外の事態に、直後から市場はパニックに陥り、世界経済への長期的な影響は計り知れないとの指摘が根強い。
世界5位の経済規模を持つイギリスが、長い歴史を経てようやく統合を果たしたEU市場から離脱することの市場への影響や経済的な損失は当然大きい。また、それがEUの将来に暗雲を投げかけていることも確かだろう。
しかし、もしかすると今回のイギリスのEU離脱、とりわけ国民投票という直接民主主義による意思決定は、これから世界の民主主義が根底から変質していく上での大きな分水嶺として、歴史に刻まれることになるかもしれない。
人、モノ、カネが国境を越えて自由に交錯するグローバル化が進み、世界中で貧富の差が拡がる中、これまで民主主義と一体になって進んできた資本主義の原則を優先する政治に不満を持つ人の数が増えている。グローバル化は総体としては世界をより豊かにしたが、その過程で中間層を没落させ、われわれの社会を一握りの富裕層と巨大な貧困層に分断した。そのプロセスは今も続いている。
そのような状況の下で国民投票のような直接民主主義的な意見集約を行えば、数に勝る貧困層の意見が優勢になるのは時間の問題だった。そして、それがグローバル化によって現出した現状に対する強烈な拒絶反応になることも。
EUやイギリスの政治史に詳しく、今回の国民投票を現地で調査してきた国際政治学者の遠藤乾・北海道大学大学院教授は、EUに主権を握られていることに対するイギリス国民の不満が予想した以上に強かったと指摘する。今回の国民投票結果の背後には移民に対する不満があることは広く指摘されているが、これは現在のイギリス政府が好き好んで積極的に移民を受け入れているのではない。EUに加盟している以上、域内の人の移動の自由を保障しなければならないというEU縛りがあるのだ。国民の多くが不満を持つ移民受け入れ政策に対して、イギリス政府は事実上、自国の政策を選択する主権を有していない。EU本部が置かれたベルギーのブリュッセルで決められた政策に縛られ、その影響を受けることを理不尽に感じるイギリス国民が多いのは当然のことだった。
元々EUは発足当初から、加盟国の主権を部分的に制限してでも、統一した市場を維持することが、アメリカや他の地域に対してヨーロッパ諸国が優位に立つことを可能にし、結果的にそれが各国の利益に繋がるという前提があった。しかし、その後、旧東欧諸国の多くがEUに加わり、今やその数は28カ国にまで拡大している。加盟国間の格差は広がり、イギリスの場合もポーランドやリトアニアなどの旧共産圏の国から大量の移民が流れ込むようになった。ピューリサーチによる世論調査でも、旧東欧圏の新たに加盟した貧困国ではEUに対して好意的な意見が多い一方で、イギリスやフランスなどその負担を背負う側の国では、EUへの支持が年々低下していた。
アメリカでは、メキシコ移民に対する不満をぶちまけることで白人労働者層の支持を集めた不動産王のドナルド・トランプが、共和党の大統領候補になることが確定しているが、その支持層は今回のイギリスの国民投票でEU離脱を選んだ層と多くの点で共通している。イギリスの国民投票の結果についてトランプはすかさず、「イギリス国民は政府を取り戻した」と、これを讃える声明を出している。
今回のイギリスの選択は、近代国家を支えてきた民主主義と国家主権、そして資本主義のトリアーデ(3つの組み合わせ)が、同時に成立しなくなっていることを示しているのではないか。イギリスでは資本主義的な利益を度外視してでも、主権を取り戻すことが重要と考える人が過半数を超えた。今後、格差が拡がりつつある日本でも、イギリスやアメリカで起きている現象とは無縁ではいられないだろう。日本でその矛盾がどういう形で顕在化するかについては、今後注視していく必要がある。
イギリスのEU離脱という選択がわれわれに突きつける課題について、イギリスの国内事情やEUの歴史などを参照しながら、ゲストの遠藤乾氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。