TPPで日本の農業は安楽死する 
キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
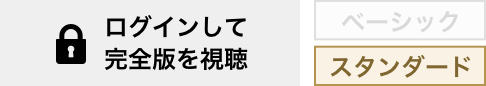



1949年神奈川県生まれ。73年東洋大学社会学部卒業。同年株式会社新農林社入社。84年同社退社後、農業技術通信社を創業。93年『農業経営者』を創刊し現職。内閣府規制改革・民間開放推進会議専門委員、行政刷新会議分科会委員などを歴任。著書に『あたりまえの農業経営』、共著に『除草剤を使わないイネつくり』など。
日本のTPP参加をめぐり、国内における論争の最大の争点となっているのが、農業の扱いだ。巷の議論では、日本の農業は競争力がないので、TPP参加によって関税が撤廃されることになれば壊滅的な打撃を受けることは必至というところだろうか。農水省などは日本がTPPに参加した場合、最大で約3兆円の打撃を受けることになるという試算まで公表している。日本の農業生産額が年間約8兆円であることを考えれば、確かにこれは壊滅的な打撃以外の何ものでもない。
それにしても、日本の農業は本当にそんなに弱いのか。
農業の現場を数多く取材し、農政問題にも詳しい雑誌『農業経営者』の昆吉則編集長は、日本人の農業に対する考え方の根底に戦後一貫して言われてきた「農家は弱者である」という先入観があり、農業には常に保護が必要とのイメージがつきまとうが、それは必ずしも現実を反映していないと、データを示しながら指摘する。むしろ問題は、農家が弱者であるという前提があってこそ成立するさまざまな利権があるために、それを維持する目的で一部の農家を弱い状態のまま維持し、保護を続ける本末転倒の政策がずっと続いているというのだ。
例えば、農水省が5年おきに実施している調査「農業センサス」の2010年版によると、日本の農家の約60%が、年間販売額100万円以下の、いわゆる零細な農家であるとされている。確かにこれでは保護が必要だと言いたくもなるデータだが、昆氏が同じデータを基に販売額ベースで再計算してみると、100万円以下の農家の売り上げは全体の6%程度に過ぎず、逆に年間1000万円以上売り上げている農家の売り上げが全販売額の6割を占めていることがわかったという。つまり、一見6割の農家のために保護策が実施されているかのように見えて、その実は市場の6%の売り上げしか占めていない生産者のために、様々な保護策がとられているのが、今日の日本の農政の実態だと昆氏は言うのだ。
なぜ日本の農政はこのように歪められてしまったのか。昆氏は「農業問題は、すなわち農業関係者問題である」と喝破する。日本の総農家戸数は約252万8千戸(2010年現在)だが、そのうち、農業を主たる生業としている生業農家は約36万戸に過ぎない。これに対して農業に関係する中央・地方の公務員や団体職員の数を足し合わせると38万5千人以上にも上るという。まじめに農業を行っている農家よりも、農業が弱いから保護しなければならないというフィクションを捏造した上で、自分たちが作り出した農業利権に群がる関係者の数の方が多いというのが、日本の農業の実情なのだ。彼らは日本の農業が保護や助成の対象となり続けるためにも、これからも日本の農業が弱いものであり続けてくれなければ困るのだ。
それでも昆氏はTPPという黒船に直面した今こそ、日本の農業にとって千載一遇のチャンスであると語る。日本は政治的な理由、とりわけ選挙での農業票の存在ゆえに、自らの力で農業利権にメスを入れることが長らくできなかった。そのため、まじめに農業を行おうとしている主業農家や経営の合理化や大規模化を通じて競争力のある農業ビジネスを営もうとしている若い農業従事者たちに、これまで十分にチャンスを与えることができない面が少なからずあった。しかし、TPPという外圧に瀕した今、そのようなことは言っていられなくなった。今こそ、後継者のいない農家から農耕地を借り受けたり、作業を請け負ったりしながら生業農家が規模を拡大させ、作業の効率化を図ることで、海外と競争していける農業を育てていくことが可能になっていると、昆氏は言う。
十把一絡げに「農業は弱い」で括ってきたわれわれの農業に対する誤謬を排し、その背後にある農政の病理や日本の農業の本当の実情、そして実力について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、ゲストの昆氏と議論した。