なぜ立憲民主党は自公批判層の受け皿になれなかったのか 
元衆院議員



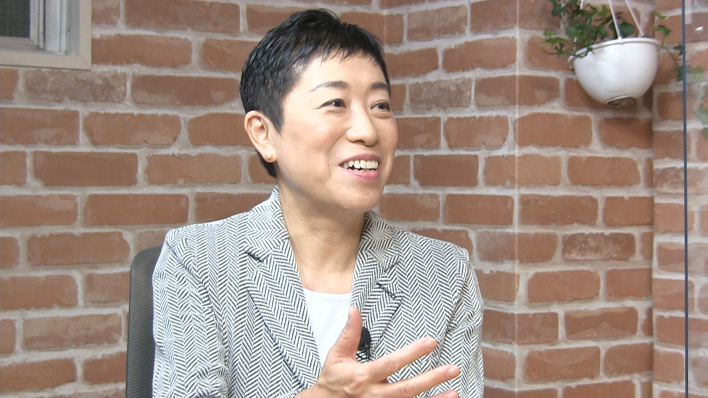
3年半ぶりに国会に戻ってきた社民党の辻元清美氏は、今の国会の雰囲気を「つるつるしている」と表現する。抵抗勢力が一掃され、誰も言うべきことを言わなくなっているという意味だ。
2002年に秘書給与の詐欺事件で議員辞職に追い込まれ、昨年9月の郵政民営化総選挙で返り咲いた辻元氏は、元来、歯に衣着せぬ言動で幅広い支持を得てきた。その辻元氏が、現在の国会を「物が言いにくくなっている」と評していることの意味は重い。先の総選挙での自民党の地滑り的勝利や、郵政民営化に対する反対した同党議員に対する容赦ない厳しい粛正に加え、国会の2割近くを占める小泉チルドレンの存在などによって、本来言論の府でなければならないはずの国会が、今や「物言えば唇寒しの府」と化してしまっているというのだ 。
辻元氏が所属する衆議院の憲法調査委員会も、国民投票法案と呼びながらその実は改憲発議を行いやすくする条項を法案の中に忍ばせていたりする。にもかかわらず、そのことに異議を唱える議員もほとんどいない。メディアがその問題を指摘することもない。
しかし、そのような政治状況の中にあっても、野党は結束して対立軸を示すことさえできず、最大野党の民主党はむしろより自民党との差を無くすことによって、政権に近づこうとしていると、野党の現状にも批判的だ。
では、現在の政治情報をどのように打破すればいいのだろうか。辻元氏は今こそ社民主義の理念を再興する必要があると説く。国内外の新自由主義的な流れで広がる社会的格差やアメリカ一辺倒の外交政策などに抗うためには、ヨーロッパ型の社民主義的理念に基づいた政治を行う必要があると言うのだ。
しかし、キリスト教や階級社会、そして成熟した市民社会の伝統に根ざしたヨーロッパ型の社民主義が、本当に日本で実現可能なのだろうか。そのような理念を日本に適用した場合にどのような問題が生じるだろうか。理念的な話よりも一つ一つ政策を積み上げていく先に答えがあるとの立場を取る「辻元流社民主義のすすめ」を議論した。