早急に支援体制を作らなければ災害関連死は防げない 
医師、日本在宅ケアアライアンス理事長
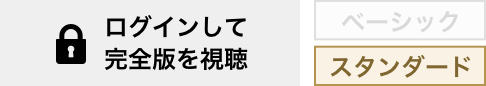



1970年神奈川県生まれ。93年青山学院大学法学部卒業。同年トヨタテクノクラフト入社。2016年株式会社「赤尾」に入社し現職。
人口8,000人という福島県国見町。ここで12台の高規格救急車の開発・製造をして近隣自治体にリースするという事業が2022年9月、町議会で承認された。大手企業による企業版ふるさと納税を原資にするため、町からの予算の持ち出しはないという、当初は国見町にとってもいい話のように見えた。ところがその後、この事業を町と一緒に進めていた会社社長の「超絶いいマネーロンダリング」、「自治体を分捕る」といった発言が報道されたため、契約は解除され、官製談合防止法違反の疑いで百条委員会が設置されることになった。
7月に公表された百条委員会の報告書によると、議会で事業が承認される半年前に、ある大手企業から匿名の企業版ふるさと納税があり、その希望分野が「災害・救急車両の研究開発・製造を通じた地域の防災力向上に向けた取り組みに関すること」と指定されていた。町議会で予算が確定したあと、その大手企業と関連する救急車ベンチャー企業が、先述の「高規格」救急車の開発・製造、及びリース事業を一社のみの競争入札で落札しており、そこに官製談合があった疑いが持たれているのだ。
企業版ふるさと納税とは、正式には「地方創生応援税制」と呼ばれるもので、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対して企業が寄付を行った場合に、法人税などから最大で寄付金額の9割までが軽減されるという制度。内閣府のサイトでは企業側には各地域の取り組みに貢献しながら税の軽減効果が得られるというメリットがあることが謳われている。制度は2016年に内閣府主導で創設され、2023年度の寄付総額は前年度比約1.4倍の約470億円まで膨れ上がっている。
特定の自治体にふるさと納税を行うことで、その企業は税額控除などによって寄付金額の9割までを回収できることに加え、国見町のように見返りに事業を請け負うことができれば、いわば2度おいしい思いができることになる。まさにそこが事業者にとって「超絶いいマネーロンダリング」たる所以だ。その一方で、寄付を受けた自治体側は新たな財源を得ることができる。それだけ聞くとwinwinの関係のようにも聞こえるが、国見町のように寄付した企業に事業の発注という形で還元されてしまえば、本来は法人税として納付されるべき税金が、最終的には寄付した企業の売り上げに化けるものであり、また寄付した事業者が無競争で事業を請け負う「官製談合」や「癒着」の温床ともなり得る危うい制度でもある。
人口減少自治体、ふるさと創生、地域の防災力、レジリエンス、官民共創…。今、注目されている用語が飛び交う中で国見町という小さな自治体で起きたできごとは、一自治体だけの問題では収まらない重大な事態となる恐れがある。いや、既に全国で同じようなことが起きている可能性も否定できない。
しかし、そもそもなぜ救急車なのか。
その背景には、救急車には国の規格がなく、自治体任せになっていることがあると、救急車製造に携わって30年になるという内尾公治氏は指摘する。大学卒業後トヨタの関連会社で救急車の製造に関わってきた内尾氏は、大手メーカーの限界を感じ現在の会社で、要望に応じたカスタムメイドの救急車作りを続けている。
総務省消防庁が高規格救急車と呼んでいるものは、救急救命士が活動している救急車のことで、その意味ではすでに自治体所属の救急車のほとんどが高規格救急車だ。しかし、車自体に「高規格」の基準はなく、現在は認定制度もなくなったため、カタログなどでは「高規格準拠」という定義のないあいまいな表現が使われている。広域事業組合も含め現時点では全国で700あまりの自治体が競争入札で高規格救急車を購入しているが、特に基準がないために車両の質は問われず、価格のみの競争になっているのが実情だと内尾氏はいう。
国見町の場合は、高規格救急車の規格がないことを逆手に取り、そのあいまいさをつく形で12台もの高規格救急車の開発・製造、そしてそのリースを新規事業として持ち込んできた事業者の話に簡単に乗ってしまったのかもしれないと、河北新報のスクープ記事でこの事態を知った内尾氏は語る。その意味では国見町も食い物にされた被害者だったのかもしれないが、同時に美味い話にはもっと気を付けるべきだった。
海外では救急車は安全性や換気、室内温度などの基準が数値で決められているほか、メーカー間の競争もあるため、救急車自体が大きく進化しているが、日本ではそもそも基準がなく、市場もトヨタと日産の独占となっていて競争がないことで、日本の救急車は海外で通用しない質の低いものになっているのが実情だそうだ。
今日、救急車はかつてのように事故や急病の患者を搬送するだけでなく、車内で救急救命士による応急処置を受けたり、医師が同乗して長時間搬送するなど多様な目的がある。新型コロナの感染が拡大する中で活躍したECMO(エクモ)カーもその1つだ。救急車自体も状況の変化に合わせて工夫が重ねられ、より安全により確実に患者の命を救うものになっていかなくてはならないと内尾氏はいう。
われわれの誰もがいつ救急車のお世話にならないとも限らない。その時に救急車のスペックによって助かる命が助からなくなる可能性だって大いにある。今も医師や救急救命士の要望を聞きながら、手作りでカスタム救急車の製造に取り組む内尾公治氏と、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が、そもそも救急車に今何が起きているのかや、救急車行政の問題点、企業版ふるさと納税の危うい点などについて議論した。


