コロナが再定義する大学とグローバル化の行く末 
東京大学大学院情報学環教授
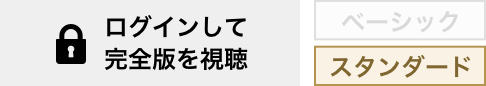



1955年愛知県生まれ。79年名古屋大学法学部卒業。86年同大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(教育学)。専門は教育行政学、教育法学。名古屋大学教育学部助教授、同大学大学院教育発達科学研究科教授などを経て2020年より現職。同年より名古屋大学名誉教授。著書に『国家と教育 愛と怒りの人格形成』、『考えよう!子どもの貧困』など。
教員の長時間労働が問題になっている。同時に、全国的な教員不足も起きている。文科省の調査では2021年4月時点で、小中学校の教員不足は2,000人あまり。この数字はその後も改善していない。
建設業や自動車運転業務、医師の時間外労働の上限規制がこの4月から始まることで、それらの業界の人手不足の深刻化が予想される「2024年問題」が取り沙汰されている。これは、「働き方改革」の一環で2019年に労働基準法が改正された時、5年の猶予期間を与えられていた業種の上限規制が始まるというものだ。
教育現場でも2019年、「学校における働き方改革答申」というものが出された。勤務時間の上限などを定めた指針が策定されるなどの対策が行われてきたが、それから5年たった今も、教師の長時間労働は続いている。病気による休職者は相変わらず増え続け、教職志願者は減り続けている。
この5年間で、部活動の見直しや支援スタッフの充実などそれなりの取り組みは行われてきた。それでも、文科省の実態調査では昨年度、教員の労働時間の平均は1日あたりおよそ11時間になっており、残業が常態化している。2016年度と比較すると在校時間は30分ほど短くはなっているが、その分、持ち帰りの労働時間が増加している。休日勤務などと合わせると、月80時間と言われる過労死ラインを超えて働く教員も多数いると見られ、勤務時間の上限をガイドラインで規制する今のやり方では不十分であることは明らかだ。
この問題は政府も認識しており、2月14日には中教審で教師の処遇改善のあり方の議論が始まっている。さらに、昨年の骨太方針を受けて、政府は2024年度から3年間を集中改革期間として、小学校高学年の教科担任制の強化や教員業務支援員の配置拡大などを進めるとしている。
しかし、今のやり方を進めるだけでは問題は改善しないと、教育行政学が専門で愛知工業大学教授の中嶋哲彦氏は訴える。中嶋氏は、教育研究者有志20人が呼びかけ人となって行った「教員の長時間勤務に歯止めをかけ、豊かな学校教育を実現するための全国署名」18万筆あまりを2月15日に文科省に届け、抜本的な改善の必要性を訴えている。
現在の法律のもとでは、教員は残業をせざるをえない制度設計となっていると中嶋氏は言う。なぜなら、1971年に制定された給特法という法律のもとでは、教職調整額として4%が支給される代わりに、時間外勤務手当や休日勤務手当は支給されない仕組みになっているからだ。残業手当が発生しなければ、残業を減らすインセンティブは働きにくい。また、仮に調整額を10%に引き上げても、それはむしろ長時間残業を後押しするだけで、勤務時間削減のインセンティブにはならないと中嶋氏は指摘する。
さらに、教職員定数の標準を定める義務標準法という1958年に成立した法律が、教員の労働時間削減の足枷になっている。その法律の下では、教員の数は児童生徒数、学級数に応じた定数配分となっていて、業務量に応じた数になっていない。そもそも教師1人当たりの持ちコマ数が多く設定されているため、教科の準備や研修などに充てられる時間がほとんどとれなくなっているという。
未来を担う子どもたちと向き合う教員たちが生き生きと仕事をするためには、今の働き方改革ではなく、制度や学校経営側の「働かせ方改革」こそが必要だと訴える中嶋哲彦氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。


