自宅療養で医療の空白を作ってはならない 
医師・日本在宅ケアアライアンス理事長
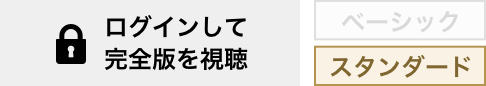

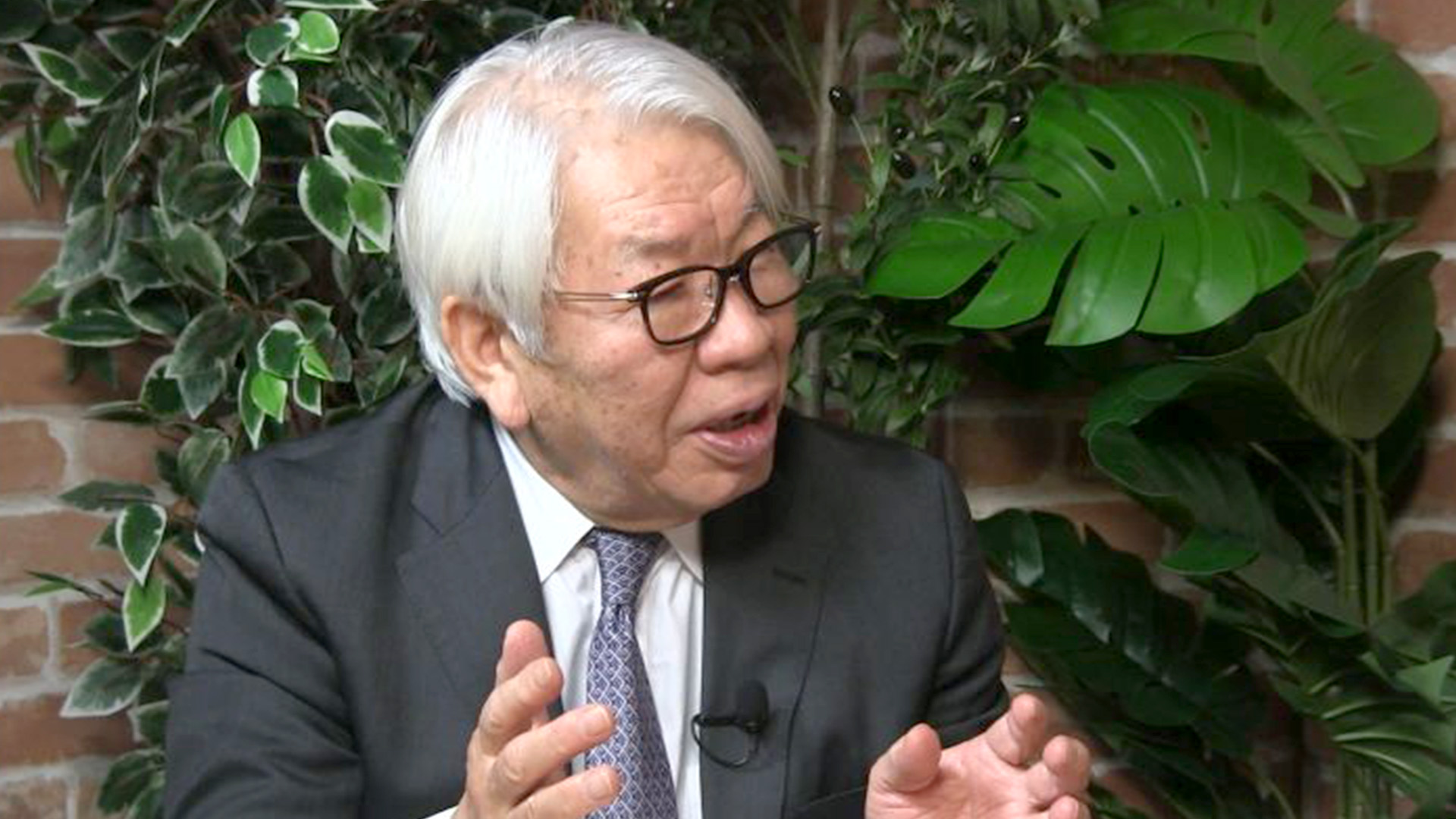
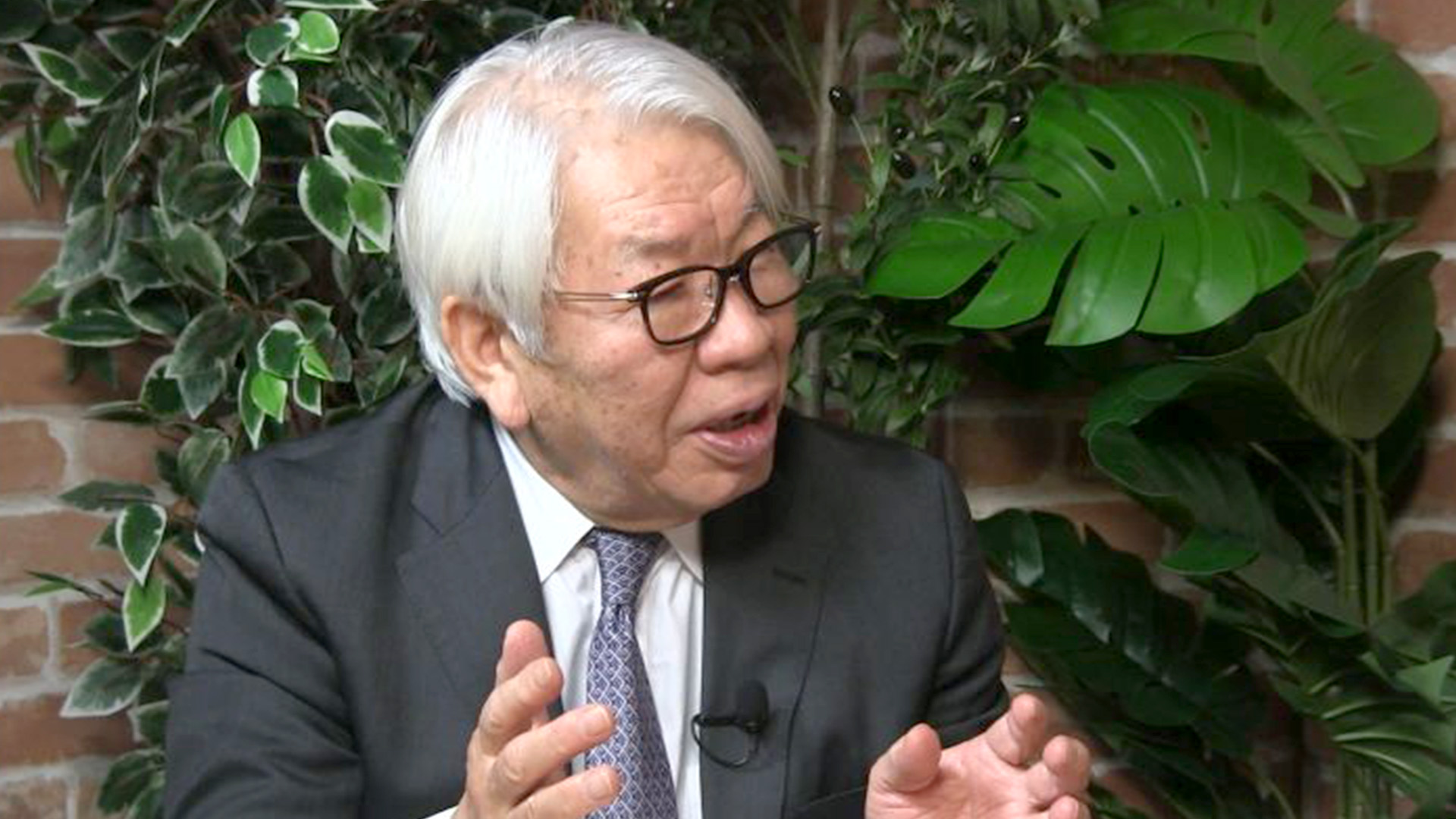
1944年岐阜県生まれ。67年早稲田大学第一商学部卒業。79年帝京大学医学部卒業。医学博士。帝京大学医学部付属病院第一外科、同救急救命センター、新行徳病院外科部長などを経て90年、東京・国立で新田クリニックを開業。日本在宅ケアアライアンス理事長、全国在宅療養支援医協会会長などを兼務。著書に『家で死ぬための医療とケア』、『口から食べるを支える』など。
元日に能登半島を襲った最大震度7の地震は、建物の倒壊、土砂災害、津波、火災などで甚大な被害をもたらした。1月19日の時点で報告されている死者数は232人。この中には地震発災後に亡くなった、災害関連死と認定された14人も含まれている。
今後、災害関連死をどう防ぐかが、大きな課題となる。
災害関連死は、阪神・淡路大震災以来、繰り返し問題とされてきた。震災を生き延びながら、その後、支援が行き届かずに亡くなる人が後を絶たないのだ。その中には避難所での感染症まん延、厳しい寒さによる低体温症、同じところにじっとしていることから起こるエコノミークラス症候群、誤嚥性肺炎などが含まれる。ことに高齢者にとっては避難生活がそのまま健康を害することにつながる場合が多い。
19日午後2時の段階で、避難を続けている人は石川県の発表で県内の359カ所の避難所に1万4,000人。その多くは家が倒壊したり、ライフラインが途絶えて自宅での生活が困難になっている人たちだ。金沢市内などに設けられた1.5次避難所や、ホテルや旅館などに二次避難した人たちもいる。
災害関連死を防ぐために、全国から医療や福祉の関係者が支援に入り避難生活を支えているが、支援の手が届かない被災者が大勢取り残されている。
ビデオニュースでは、1月13日から14日にかけて、避難所や介護施設や自宅で寒さと雪や雨の中、必要な医療支援を受けられていない高齢者の現状を把握し、支援につなげるために被災地に入った医師の新田國夫氏に同行し、高齢化率50%を超える能登半島北部の穴水町、能登町を訪ねた。
地震発生から約2週間が過ぎても、施設で暮らしていた高齢者たちは苛酷な状況に置かれていた。地震までは普通に歩いていた人たちが雑魚寝状態の狭い部屋の中で寝たきりになり、そこに追い打ちをかけるように新型コロナの感染が広がっていた。起き上がることができずに大きな褥瘡(床ずれ)ができている高齢者もいた。
さらに、介護が必要な高齢者を抱えているために避難所に行けない人たちもいた。われわれが訪ねるまで支援者は誰も来ておらず、電話も通じずテレビも見られないという状況に置かれていた。介護事業所も被災し、これまで当たり前に利用できていた介護サービスはストップしていた。在宅避難をして困っている世帯がどのくらいあるのかは行政でも把握できず、地域の介護関連のリソースがどのくらい被災し今後の見通しがどうかもまだ把握されていなかった。
在宅療養支援医協会会長で在宅ケアに取り組む新田氏は、特に高齢者の場合は、急性期のDMATなどの医療派遣から、生活を支える医療に早い段階から移る必要があるが、それが難しい状態にあると指摘する。医療や看護、介護など多くの団体が被災地に入り支援を行っているが、それでも必要な支援が届かない人たちが大勢いる。東京郊外の国立市で地域包括ケアに取り組んでいる新田氏は、地域全体を面でとらえ生活を支える仕組みをつくらないと災害関連死は防げないだろうと語る。
震災を生き延びた被災者たちを災害関連死から守るために今、何が必要なのか。高齢者を支えるケアに詳しい新田國夫氏と、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が議論した。


