日本人はまずパレスチナで何が起きてきたかを知らなければならない 
国際政治学者、放送大学名誉教授
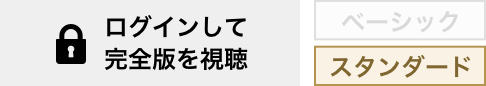



1982年岐阜県生まれ。2004年東京外国語大学外国語学部卒業。10年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門はロシア・ユダヤ史、パレスチナ問題、シオニズム。エルサレム・ヘブライ大学人文科学部博士研究員、ニューヨーク大学ヘブライ・ユダヤ学科客員研究員、埼玉大学研究機構准教授などを経て16年より現職。著書に『イスラエルの起源 ロシア・ユダヤ人が作った国』、『ロシア・シオニズムの想像力』など。
結局、戦闘停止期間は7日間で終わり、12月1日から再びイスラエルによるパレスチナへの攻撃が再開されてしまった。それにしても、世界中から批判を浴びても、今なおパレスチナへの攻撃の手を一向に緩めようとさえしないイスラエルの論理とはどのようなものなのか。
イスラエルによる人道を無視した激しい攻撃には、中東諸国はもとより、当初はイスラエルに寄り添う姿勢を見せていた西側諸国の中にも懸念を表明する国が1つまた1つと増え始めている。しかし、当のイスラエルは国際的には後ろ盾となっているアメリカの自制要求をも振り切り、ガザへの爆撃と侵攻を続けている。もともとイスラエルにパレスチナの土地の分割を認める決議を採択し、イスラエル建国の礎を作った国連の意向さえ、まったく意に介さない姿勢を見せている。
今回のイスラエルのパレスチナ侵攻が、10月7日のハマスによるテロ行為への報復であり、イスラエルにとっては自衛権の行使の範疇とされているのは理解できる。しかし、とはいえ火力で何百倍も優るイスラエル軍による、多くの一般市民が暮らすガザ市街地への容赦無い攻撃は、誰がどう見てもあらゆる国際法に違反する蛮行との指弾を免れないものだ。
元々パレスチナ問題は、主にアラブ系のイスラム教徒であるパレスチナ人が住むパレスチナの地に、2000年以上前に王国を滅ばされディアスポラとなって世界中に離散していたユダヤ人たちが入植し始めたことに端を発する。その後、イギリスによる無責任な委任統治などの悪影響もあり、パレスチナにおけるパレスチナ人とユダヤ人の間の摩擦は入植するユダヤ人人口の増加に比例するかのように拡大していった。1947年に国連が領土をほぼ半分ずつに分ける分割決議を採択したが、その直後に国家を建設したイスラエルが軍事力を背景に支配地域を拡大していった結果、今やパレスチナ全体でパレスチナ人が自治権を有している領土は全体の8%にまで激減している。
その後、1993年のオスロ合意など、何度か両者を和解させる試みがあったが、その後もイスラエル軍は侵攻して奪った土地から撤退しないばかりか、その後も入植を続け領土を拡大していった。今回の紛争の直接の火種がハマスによるテロ行為だったことは確かだが、そこに至る過程でイスラエルがパレスチナを徹底的に追い詰めてきたこともまた紛れもない歴史的事実だ。
東京大学教養学部の准教授でユダヤ人の歴史が専門の鶴見太郎氏は、今回ハマスがなぜあのような蛮行に手を染めたのかを理解するためには、過去50年にわたりパレスチナで何が起きてきたかを知る必要があるのと同様に、イスラエルの行動原理を理解するためには、イスラエル人口の7割を占めるユダヤ人たちが、18世紀以降世界でどのような仕打ちを受けてきたかを知ることが不可欠だと語る。
ユダヤ人に対する迫害というと600万人とも言われる犠牲者を出したナチスドイツによるホロコーストがあまりにも有名だが、実際はユダヤ人はそれ以前から世界各地で迫害を受けてきた。特に19世紀に入り世界各地でナショナリズムが台頭すると、異民族でありながらその国々で経済的な力を得ていたユダヤ人への風当たりは俄然強くなった。ロシア帝国下で発生したポグロム(ユダヤ人に対する襲撃事件)に端を発するユダヤ人の迫害では6~20万人ものユダヤ人が殺害されたとみられるが、世界はこれを黙殺し、事実関係の調査さえなされていない。
鶴見氏は、国際社会がポグロムをなかったことにして誰にも責任を取らせようとしなかったことで、イスラエルは国際社会に対して揺るぎない不信感を持つようになったと指摘する。そして、ユダヤ人の伝統的な「迫害されても抵抗しない」姿勢が、結果的にポグロムの犠牲者を拡大させたとの反省から、自分の身は自分で守らなければならないと考える人がユダヤ人の、とりわけパレスチナの地に戻って新しい国の建設を掲げるシオニストたちの間で主流になっていった。そしてその象徴の1つが、強い軍隊を持ち、攻撃されたら徹底的に反撃することだった。その結果、ユダヤ人たちは自分たちの国家を建設し、それを守ってくることができたとの自負を、今も多くのイスラエル人が持っているのだという。
しかし、もし純粋に地政学的な判断で動いているとすれば、元々その地に住むパレスチナ人を過度に追い詰めることは、決してイスラエルにとっても得にならないという判断ができるはずだが、イスラエルがパレスチナの地からパレスチナ人を一掃することの正当化に宗教的な教義を持ち出すようになったことが、状況をますます困難にしている。もともとユダヤ教は「メシアが降臨したらエルサレムに集まる」ことが教義に定められていたが、それをユダヤ教の指導者たちが反転させ、「自らエルサレムに行く努力を見せればメシアが早く降臨する」に教義そのものを変えてしまったのだという。パレスチナの地、とりわけエルサレムをユダヤ人が完全に支配することがメシアの降臨を早めると真面目に信じているユダヤ人は決して少なくないのだという。
このような歴史的な紆余曲折を経て今日にいたるパレスチナ問題は、とても短期間で解決できるものではなく、長期的な解決策を模索するしかないと鶴見氏は言う。その際、最も重要なカギを握るのが、イスラエルの国際社会に対する信頼を取り戻せるかどうかだ。ユダヤ人に対する度重なる迫害が行われても、それを黙殺した国際社会に対するイスラエルの不信感は根強い。それが、自分のことは自分で守るしかないという過度の自衛意識を芽生えさせ、いかなる攻撃に対しても百倍返しをしなければ国が滅ぼされてしまうという切実な恐怖感をイスラエル人の心に抱かせている。その心の問題を解決しない限り、パレスチナ問題を解決することは難しいだろう。また、同時に、パレスチナ側に怨念の連鎖を生まないためにも、常にイスラエルからの脅威に晒され、多くが身内の誰かがイスラエルによって殺されたり暴力を受けたりした経験を持つパレスチナ人の心のケアも国際社会が取り組まなければならない重要な課題になると鶴見氏は言う。
イスラエルが国際社会から指弾されてもガザへの攻撃の手を緩めようとしない理由や、イスラエルのユダヤ人たちが歴史上、世界の方々でどれだけの迫害を受け、それが現在のイスラエルという国の自衛意識にどのような影を落としているのかなどについて、東京大学教養学部准教授の鶴見太郎氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。


