日本の障害者施策は世界基準とどこがずれているのか 
日本障害者協議会代表
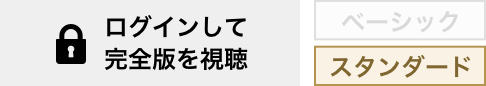



1952年岩手県生まれ。77年中央大学法学部卒業。80年司法試験合格。83年弁護士登録。86年新里・鈴木法律事務所を設立。専門は借金・多重債務問題、消費者被害。著書に『社会を変えてきた弁護士の挑戦 不可能を可能にした闘い』、共著に『武富士の闇を暴く』など。
旧優生保護法のもとで行われた強制不妊手術について、被害者が国に対し損害賠償請求を起こした仙台訴訟から5年余が過ぎた。現在、全国12の地裁・支部で35人の原告が争っているが、原告はみな高齢ですでに5人が亡くなっている。
旧優生保護法は一般的には中絶を可能にするために作られた法律として受け止められてきたが、その一方でこの法律は、1996年に母体保護法と名前を変えるまで、優生思想に基づいた法律でもあった。実際、この法律の第一条の「目的」には、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と書かれており、別表としてその対象となる病名や障がいの種類が列挙されている、人権侵害が甚だしい法律だったのだ。
この法律の下で行われた不妊手術と中絶手術の被害者数は8万4,000人に及ぶ。そのうち、同法4条に基づき本人の同意なく強制不妊手術を受けさせられた人の数は、厚労省の資料によると1万6,475人にのぼる。その対象は遺伝的疾患とされる病気のほか、聴覚障がいや知的障がい、知的障がいと見做された人、医療事故による後天的な障がい、さらには素行が悪い人まで広範に及ぶ。優生保護法被害全国弁護団共同代表で弁護士の新里宏二氏は、国にとって不都合と考えられた人たちが手術の対象にさせられていたのではないかと指摘する。
2019年5月に最初に判決が出た仙台訴訟は、同法を憲法違反だったと認めたものの、提訴権の行使が認められている20年の除斥期間を過ぎていることを理由に損害賠償の認定までは踏み込まなかった。そしてその後、他の地域で起こされた裁判でも同様の判決が続いた。ところが去年、大阪高裁は憲法違反の法律のもとで行われた強制不妊手術に対して「除斥期間の適用を認めることは著しく正義・公平の理念に反する」として、一連の裁判では初めて国に賠償を命じる判決を下した。その後、4つの高裁で原告勝訴の判決が続いた。しかし、国は裁判所によって除斥期間の判断に差異があることを理由に、これらの判決を受け入れず上告している。
旧優生保護法は法改正が1996年まで行われなかったことや、そもそも資料が残っていないなどの理由から、自身の身に起きたことの意味を知らずに生きてきた被害者も多い。そのような理由で訴えを起こすことができなかった被害者が多くいる中で、国が除斥期間を主張することにどんな意味があるのだろうか。
全面解決を強く訴える原告の一人で14歳のときに知らないまま強制不妊手術を受けた北三郎さん(仮名)は、不妊手術は親にさせられたと思い込み親を恨んできたという。優生保護法という法律のもとで行われたことを知ったのは仙台訴訟が提起されたことを新聞で読んだ5年前のことだった。
戦後に新しい憲法のもとで成立した優生保護法は、女性議員と医師議員が主導した議員立法第一号だった。今後に同様のことを起こさないためにも、人権意識が欠如したまま過った政策が長く続いてしまった経緯を総括し、これ以上裁判を引き延ばすことなく被害者に対して国として謝罪するべきではないか。
6月1日には、最初に提起された仙台訴訟の高裁判決が予定されており、その判決とその後の政府の対応に今、あらためて注目が集まっている。弁護団の団長である新里宏二氏に、当事者の思いや背景にある日本社会の課題なども含めて、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が聞いた。


