患者に必要な薬が届かなくなっている現状を看過することはできない 
元厚労省医薬・生活衛生局長、岩手医科大学医学部客員教授
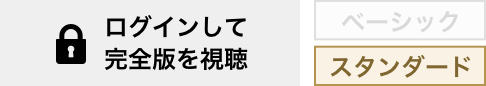



1959年岩手県生まれ。83年東京大学法学部卒業。同年、厚生省(現・厚生労働省)入省。政策統括官(社会保障担当)、医薬・生活衛生局長、医政局長などを経て2018年退官。19年より現職。20年より日本在宅ケアアライアンス副理事長。
3年に及ぶコロナ禍は「かかりつけ医」の重要性と、それを持たないことのリスクを浮き彫りにした。
コロナの流行が始まった当初、政府は発熱したらまずかかりつけ医に診てもらうよう繰り返し発信した。しかし、その段階でかかりつけ医を持つ人が果たしてどれほどいただろうか。期せずして国民の間に戸惑いや混乱が広がり、かかりつけ医を持たない人からの問い合わせが保健所に殺到。日本中で保健所機能がパンクするという苦い経験したことは記憶に新しいところだろう。
しかし、その後、かかりつけ医制度をめぐる議論はどうなったのか。
昨年5月、財務省の財政制度等審議会がかかりつけ医機能の法制化や認定制度などを求める建議を打ち出した。しかし、直ちに日本医師会が法制化反対の意向を示したため、その後の議論では 「かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行う」という回りくどい表現が用いられるようになったことは、すでにマル激でお伝えした通りだ。その後、全世代型社会保障構築会議や社会保障審議会などでの議論を経て、昨年末には一応、制度化へ向けたとりまとめが行われている。
しかし、この「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」とは何なのか。
昨年の取りまとめでは、医療機能情報を提供する制度を利用して法律で「かかりつけ医機能」を定義した上で、都道府県が情報提供をすることや、かかりつけ医機能の報告制度を創設し地域ごとに協議をする、などとしている。しかし、そもそも「かかりつけ医」とは何なのかが国民に共有されていない中で、「かかりつけ医」と「かかりつけ医機能」の違いは何かなど、医療を受ける側の国民にとってはわかりにくい議論となっている。ここまでの議論は医師会などの医療提供者側や制度をつくる行政側の視点で議論されており、肝心の患者が置き去りにされている誹りは免れない。
かつて厚生労働省で医療政策を担う担当部署の厚労省医政局の局長を務めていた武田俊彦氏は、かかりつけ医を巡る議論は今、重要な局面を迎えていると語る。コロナ禍で起きた医療の空白をなくし、患者が常に医療とつながっている安心感を持てるようにするためにも、かかりつけ医に相談できないためにいたずらに救急車を呼んだり保健所に問い合わせが殺到するような事態を減らし医療現場の負担を減らすためにも、かかりつけ医の議論を一つずつ整理して前に進めていく必要があると指摘する。
いくらかかりつけ医の機能を法律で決めても、医療を提供する側の能力と意欲がついてこなければ、制度が機能しないのは言うまでもない。一方で、患者側がかかりつけ医に何を望みどう選択するかによっても、制度の意味は変わってくる。法律を変えれば医療者や患者の行動が自動的に変わるわけではない。まずは制度化によって何を目指しているのかが国民や医療関係者の間で広く共有されない限り、この制度は絵に描いた餅に終わりかねないと、武田氏は危惧する。それを避けるためには今、現場との対話が何より必要だ。
確かに、かかりつけ医機能のハードルを上げると、担い手となる医療機関は減るかもしれない。また、逆にハードルを下げ過ぎると、患者側の不満が大きくなる可能性がある。武田氏は昨年、東京の救急搬送が過去最多になったことを指摘した上で、特に、日常的に医療のお世話になることが少ないためにかかりつけ医を持たず、結果的にコロナ禍で医療から置き去りにされた経験を持つ若い世代に向けて、かかりつけ医にどのようなメリットがあるのかをわかりやすく説明していく必要があると訴える。しかし、患者に安心感を与えられる医師がいて、様々なかかりつけ医機能を連携させて地域で担っていく仕組みをどう構築していくのかについては、まだまだ具体的な方策は見えていない。
コロナ禍の教訓を活かす意味でも、今日本に求められるかかりつけ医制度とはどのようなものなのか、それを実現するために何をしなければならないかなどについて、医療行政に詳しく在宅ケアに携わる医療・介護関係者の信頼も厚い武田俊彦氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。


