「年収の壁」と「働き控え」を克服するためのベストな方法とは 
大和総研主任研究員
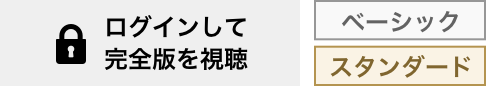



1971年兵庫県生まれ。94年京都大学法学部卒業。同年朝日新聞社入社。つくば、浦和支局を経て、99年より政治部。政治部次長(デスク)、特別報道部デスクなどを歴任。2014年吉田調書報道を巡る一連の懲罰人事で特別報道部デスクを解任される。21年退職しフリーに。現在、個人ニュースサイト「Samejima Times」を主宰。13年「手抜き除染」報道で新聞協会賞受賞。著書に『朝日新聞政治部』。
長らく日本のリベラル言論をリードしてきた朝日新聞が、危機的な状況に陥っているという。1990年のピークから20年にわたり誇ってきた800万の発行部数も、ここ10年はつるべ落としのように急落を続け、2022年には約半分の400万部あまりまで激減し、2021年度にはついに400億円を超える大赤字に転落してしまった。ほぼ同時期に他の新聞社も軒並み発行部数を落としているが、その中でも朝日の凋落ぶりは群を抜いている。
朝日新聞の発行部数が激減するようになった直接のきっかけとしては、2014年に相次いで発覚した「2つの吉田問題」が挙げられることが多い。これは2011年の東日本大震災に起因する原発事故をめぐり、当時福島第一原発の所長だった吉田昌郎氏が政府事故調に対して語った調書をめぐる「吉田調書」報道と、文筆家吉田清治氏の従軍慰安婦に関する証言をめぐる「吉田証言」報道がいずれも不適切なものだったことが指摘され、最終的には朝日側も自らの非を認め記事を撤回したというもの。2つの吉田報道は問題の性格こそ異なるが、いずれの場合も原発や従軍慰安婦問題に対する朝日新聞のイデオロギー的な偏向が誤報や不正確な報道を招いたとして、特に安倍政権を筆頭に保守派からの厳しい指弾に晒された。
確かに朝日新聞が伝統的に持つリベラル色の強い思い入れが、2つの吉田報道に多少なりとも影響を与えた面はあったかもしれない。しかし、吉田調書がスクープされた当時、記事を担当した特別報道部のデスクという当事者の立場にあり、問題の責任を取らされる形でデスク職を解任されたばかりか報道とは無縁の部署に飛ばされた、元朝日新聞記者の鮫島浩氏は、一連の問題は朝日のリベラリズムに起因するものなどではなかったと言い切る。リベラルだから叩かれると思われている朝日新聞という組織の実態は、実際には権威主義の塊であり、社内には報道部門であってもサラリーマン根性丸出しの官僚主義と出世至上主義や事なかれ主義が隅々まで蔓延している。それが朝日では多くの問題を生んでいると鮫島氏は言う。
朝日新聞は当初機密扱いされていた吉田昌郎氏の調書を独自に入手した結果、吉田所長が原発の所員たちに原発内に留まるよう待機命令を出していたにもかかわらず、ほとんどの隊員が約10キロ離れた福島第二原発まで撤退していたことを突き止め、これを「命令違反し撤退」と報じた。しかし、事故発生直後の混乱の中で、福島第二原発まで撤退した所員たちの中には所長の命令を知らなかった人もいたかもしれないなどの指摘があり、それを一律に「命令違反」と切り捨ててしまうのはやや乱暴ではないかという声が朝日の社内からもあがっていた。
確かにこの報道は、原発事故に直面し困難な決断を迫られている東京電力の職員への配慮に欠けた表現があったかもしれない。しかし、記事の中に明確な誤報といえるような間違いがあったわけではなく、あくまで記事のニュアンスが東電職員への配慮に欠けているのではないかという点が問題となった。ところがこのニュアンス問題が、権威主義がはびこる社風の中で、社長にノーと言えないヒラメサラリーマンの事なかれ主義などによって、組織の屋台骨を揺るがすほどの大問題に拡大してしまったのだと鮫島氏は言う。
事の顛末の詳細は番組本編に譲るが、吉田調書報道については、記事のニュアンスに対して社内からも懸念する声があがったため、担当デスクだった鮫島氏は直ちにニュアンスを修正するための補足記事の配信を上司に提案した。しかし、当時の朝日新聞の社長がこの吉田調書のスクープ記事を新聞協会賞に応募することを決め、非常に前のめりになっていたため、社長周辺の幹部たちが、補足記事などを配信すれば記事の権威に傷がつき、それが結果的に社長の顔に泥を塗ることになるのを恐れたため、鮫島氏の提案は却下されたそうだ。
直後に補足記事を出していれば、この問題で朝日がここまで叩かれることはなかったかもしれない。しかし、その時の朝日新聞はジャーナリズムとはまったく別次元の理由で、たった1本の補足記事を出すことができなかった。
鮫島氏の話を聞く限り、今や朝日新聞という組織はとてもではないが、リベラル言論の雄を引き受けられるだけの矜持は持ち合わせていないように見える。しかし、問題は朝日がいい加減なことをやれば、これまでリベラル派からやり込められ、リベラルに対して怨念を抱く保守派は嵩に懸かって攻勢に出る。そして、朝日がむしろ社内的な理由から記事の訂正や撤回に追い込まれることにより、リベラルな主張や考え方自体が間違っていたかのようにされてしまう。日本では今もって朝日新聞は、少なくとも一部の人たちにとってはリベラル言論の象徴的な存在なのだ。それは逆の見方をすれば、朝日はもはや組織内ではリベラルメディアの体をなしていないにもかかわらず、表面的にはリベラルの旗を上げ続けることによって、日本のリベラリズムの弱体化を招いているということにもなる。
今後、朝日新聞が復活する可能性について、27年間朝日に在籍した鮫島氏はいたって悲観的だ。これだけ部数を減らし危機的な状況に追い込まれた今も、組織としての朝日は根本的には変わっていないと鮫島氏は言う。しかし、朝日を含む既存のメディアが凋落していく中、日本では彼らに取って代わることができる新しいメディアは必ずしも育っていない。記者クラブ、再販制度などで既存のメディアの権益が政府によって手厚く護られている日本では、新しいメディアが既存のメディアと公正な土壌で競争できるような環境には置かれていない。
政府から数々の特権をもらっている限り、政府に大きな借りを作っている状態が続く。政府と対等な立場での報道などできないし、自ずと自由な報道が縛られることになる。鮫島氏は朝日社内で記者クラブ依存をやめ、欧米型の特報部方式の導入に尽力したが、吉田調書報道で鮫島氏の特報部が不祥事を起こしたことにされたため、今朝日では再び記者クラブ依存体質に戻っているそうだ。
今となっては、朝日はリベラルだから叩かれるのではなく、実際にはリベラルとは真逆なことを数多くやっていながら、表面的にリベラルを気取るから叩かれるというのが、事の真相と言えるかもしれない。だとすれば、今朝日がすべきことは、言行を一致させるか、リベラルの旗を降ろすかの二択しかない。
朝日の古い体質にほとほと嫌気がさし、50歳を前に朝日を退職して自分ひとりで新しいメディアを立ち上げた鮫島氏と、なぜ朝日新聞や既存メディアは生き残れないのか、政府から数々の特権を得ながらジャーナリズムを標ぼうすることがいかに欺瞞に満ちているかなどについて、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。


