トランプのカムバックはアメリカと世界をどう変えることになるか 
上智大学総合グローバル学部教授
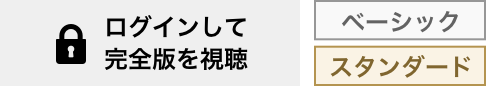



1964年沖縄県生まれ。88年琉球大学医学部卒業。米・ハーバード大学公衆衛生大学院修士課程修了。医学博士。専門は総合診療医学、臨床疫学、臨床教育。沖縄県立中部病院内科副部長、聖路加国際病院一般内科医長、地域医療機能推進機構(JCHO)本部研修センター長などを経て2017年より現職。筑波大学大学院教授、日本プライマリケア連合学会理事、日本病院総合診療医学会理事などを兼務。著書に『新型コロナウイルス対策を診断する』、『病歴と身体所見の診断学 検査なしでここまでわかる』、共著に『新型コロナウイルス感染症と自治体の攻防』など。
日本はどこでコロナ対策を間違えたのだろう。
元々日本は感染症対策の大原則として、「感染源の排除」、「感染経路の遮断」、「宿主抵抗力の向上」の3つを「感染対策の3原則」として掲げ、少なくとも過去の感染症はうまく凌いできた。この原則は今でも厚生労働省のウェブサイトに掲げられている。今回のコロナ禍で、その原則に沿って感染の抑え込みに成功している多くの国が採用しているのが、前述の3原則をコロナに転用した、「感染源の特定」「感染源の隔離」「水際の強化」のコロナ3原則だ。最初の2つは元々日本の厚労省が感染症対策の基本原則として掲げているものに過ぎないし、3番目の「水際・・」は今回のように国際的に蔓延しているCOVID-19のような感染症の場合、最初の2原則を補完する上で不可欠となる。
日本も単にそれをしっかりやればいいだけ・・・、のはずだった。特に日本のような島国は隣国と陸続きになっている国と比べると3原則の3つ目にある「水際対策」を徹底する上で、決定的に有利な立場にある。コロナの抑え込みに成功している筆頭格として常に名前が挙がるニュージーランドや台湾が島国であることは、決して偶然ではない。
しかし、今回ばかりは日本は明らかに感染症の抑え込みに失敗している。今や東京都と沖縄県は人口当たりの新規陽性者数で、アメリカやブラジル、南アフリカ、インド、インドネシアといった、かつてコロナに世界で最も苦しめられてきた地域を抜き、世界一の感染地帯になりつつある。しかも、日本では濃厚接触者が国際基準よりも遙かに狭く定義されているため、PCR検査数が圧倒的に少ない(日本ではマスクをしていれば濃厚接触者とはならず、よって身近に感染者が出てもPCR検査の対象とならないし、いわゆる社会的調査(サーベイランス)目的の検査もほとんど行われていない)こともあり、実際の感染者数は表面化している人数よりも遙かに多いと考えるのが普通だ。群星沖縄臨床研修センター長で世界のコロナ事情にも通じている徳田安春医師は、今や日本が世界のコロナ感染症の「エピセンター(震源地)」に躍り出ていると指摘する。
そもそも日本はコロナの感染拡大当初から、自ら決めた感染症対策の原則を破りまくってきた。昨年3月に中国の習近平主席の国賓としての来日が予定されていたため、安倍政権は最後まで中国からの日本入国に制限をかけようとしなかった。1月23日に中国が武漢を都市封鎖したのを受けて、アメリカは1月31日に、ニュージーランドも2月2日には中国からの入国禁止措置を発動しているが、日本が中国からの入国を制限したのはなんと3月5日である。しかもこれは、習近平主席の訪日中止が発表された翌日だった。
感染源を特定する上で必須となる検査も、安倍元首相の言葉を借りれば、正体不明の「目詰まり」のために、中々増やすことができなかった。感染源が特定できなければ、それを隔離などできるわけがない。しかも、中国からの入国が制限された後も、日本の水際対策は信じられないほどいい加減だった。
感染者を多く出している国から帰国した人は2週間の検疫が義務づけられ、空港からも公共交通機関を利用してはならないことになっていたはずだが、そのルールを行使する仕組みが事実上存在せず、すべてが本人まかせになっていた。空港の検疫で「帰り道に公共交通機関は使えませんよ。ちゃんと後ろから見てますからね」などと言われ、空港ターミナルを出てから後ろを振り返ってみても誰も見ていなかったという不思議な経験をした人は意外に多いはずだ。
そしてオリンピックだ。昨年3月末まではその年の7月からオリンピックが開催されることになっており、厳しい水際対策など夢のまた夢だった。また3月24日にオリンピックが1年延長されることになった後も、日本にとってはオリンピックが喉元に突き刺さった骨のようになり、徹底した水際強化の方向に舵を切ることができなかった。
感染源の特定・隔離も水際対策も徹底せずに、感染症が抑えられるわけがない。ただそれだけのことだ。そして日本は辛抱強い国民の自粛と、なぜか単独で槍玉にあげられることになってしまった飲食業界の多大な犠牲の下で、少なくとも最近までは欧米ほどの感染爆発を経験せずにきた。しかし、ここに来て従来株よりも遙かに感染力が強いデルタ株の登場によって、遂にごまかしがきかなくなった。かつて日本より遙かにひどい感染に喘いでいた欧米諸国の多くがワクチン接種で先行する中、感染対策が不徹底の上にワクチンでも出遅れた日本で感染爆発が起きることは避けられないことだった。
徳田氏は今こそ感染症対策の基本に立ち返り、徹底した検査による感染源の特定と隔離、そして水際対策の強化を図りつつ、ワクチン接種を迅速に進めていく以外に、日本が現在のコロナ袋小路から抜け出る道はないと語る。厚労省も掲げる感染症対策の基本原則は英語ではゼロ・コビッド(zero covid)政策やエリミネーション政策(排除政策)と呼ばれるもので、日本ではこれが「ゼロコロナ」などと呼ばれてコロナ撲滅計画であるかのように大いに誤解されているが、ゼロ・コビッドというのは要するに、感染源の特定と隔離を徹底させ、水際強化によって国外から新たに感染源が流入してくることを防ぐことで、市中感染を限りなくゼロに近づけて行こうという、至って常識的な政策ことだ。
無論、ここまで市中感染が拡がった今、ここからゼロ・コビッドに持って行くのは容易なことではない。しかも、敵は感染力の強いデルタだ。今後、更に強力な変異種が現れないとも限らない。しかし、もし「ウィズコロナ」なる政策が感染症対策と経済の両立を図ることを目的としているのであれば、ゼロ・コビッドこそその両立を図る最良にして唯一の策だと徳田氏は言う。なぜならば、市中感染をゼロにできれば、国内の経済活動はほぼ平常通り行うことが可能になるからだ。また、いざ市中感染ゼロが実現できれば、検査も通常はサーベイランス検査のみで十分となる。いわゆる社会的調査だ。そして、万が一水際でチェック漏れがあり再び市中感染が発生した場合、徹底した検査によっていち早くそれを察知し感染源を特定し、国際基準で定められた濃厚接触者の定義に則り、対象を隔離することで、市中感染ゼロを一刻も早く取り戻すよう努める。
それを実現するためには、検査体制の整備と水際対策の大幅強化、そして感染者と濃厚接触者を一時的に隔離するための施設が必要になるが、中途半端な両立策で延々と緊急事態宣言を出し続けるよりも、その方がはるかにコスト面でも優位性があると徳田氏は言う。
日本のコロナ対策はどこが間違っているのか。コロナの抑え込みに成功している国が採用している「ゼロ・コビッド」もしくは「エリミネーション」とはどのような政策なのか。今からでも日本はそちらに舵を切り直すことが可能なのか、もしそれをしなければどのような結末が待っているのか、などについて、徳田氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。


