なぜか「高規格」救急車事業が食い物にされるおかしすぎるからくり 
株式会社「赤尾」特需部救急担当
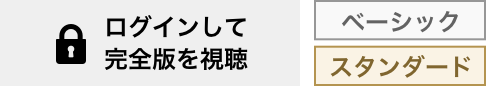



1956年神奈川県生まれ。80年東京大学医学部保健学科卒業。同年NHK入局。アナウンサー、解説委員、制作局エクゼクティブ・ディレクターなどを経て2016年定年退職。同年ビデオニュース・ドットコムに移籍。著書に『医療現場取材ノート』など。
これは無いものねだりなのだろうか。
もし日本に「家庭医」制度が確立されていれば、今回のコロナへの対応も全く違ったものになっていた可能性が大きい。発熱した人が保健所や発熱外来に電話がつながらずに何時間も待たされた挙げ句、医師でもない保健所職員の判断に従わなければならないような不合理な事態も避けられただろうし、もちろんそのせいで保健所がパンクしたり、PCR検査が一向に増えないなどという謎の現象が起きることもなかったのではないか。一度コロナに感染した患者、とりわけ高齢者が、その後、一般病棟での受け入れ先が見つからずコロナ病床に入院したままになるようなことも、かなりのケースで避けられたかもしれない。
しかし、なぜ「家庭医」という制度が日本に存在しないのか。更に言うならば、その言葉がなぜ日本では使われない、いやそれが使ってはいけない言葉になっているかを知ることで、日本の医療の実相がかなり見えてくるのではないか。
今回新型コロナウイルスの流行が始まってから、メディアはやたら「かかりつけ医」という言葉を多用するようになった。また、「プライマリーケア医」などという難しい言葉を使う人もいるが、要するにどれもこれも家庭医、いわゆるファミリードクターの事だ。しかし、医療に多少なりとも関係していたり、メディアのように多少なりともその分野の歴史的な経緯を知っている関係者たちは、決して「家庭医」という言葉は使わない。そしてそれには理由がある。
実は日本は1980年代、急速な高齢化社会を迎えるにあたり、本気で家庭医制度の導入を図ろうとしたことがあった。しかし、強い政治力を持つ日本医師会の抵抗に遭い、1987年にその試みが潰されたという経緯がある。それ以来、医療界では「家庭医」という言葉はトラウマであり禁句になっているという。
家庭医とは、一般的には家族が日常的にお世話になっているかかりつけのファミリードクターのことだが、制度としては実際にはそれ以上の意味を持つ。日本が80年代に導入しようとした家庭医制度も、イギリスのGP(General Practioner)制度を参考に、一般の市民がどんな病気にかかっても、まず最初に診断を受ける医師を予め登録し、仮にその先、大学病院や専門医に診てもらう必要がある場合でも、まずは家庭医の判断を仰ぎ、そこから紹介してもらうというような制度が指向されていた。
そもそもイギリスのGPは日本の総合診療医にあたる専門医の一種で、厳密な資格が設けられている。また、イギリスのGP制度はNHSと呼ばれる国民健康保険制度の下で、日本の国民皆保険のような保険による出来高払いではなく、GPには予め割り当てられた患者数分の基本的な診療報酬が、診察の有無にかかわらず税金から支払われ、患者は家庭医からは無料で基本的な医療サービスを受けられる包括的な保険医療制度となっている。最初に診てもらえる医師が決まっているため、その医師がたまたま多忙だと、受診できるまで何日も待たされる場合があるなどの欠点も指摘されるが、出来高払いを前提とする日本の保険制度の下では、医師は病気の患者が多ければ多いほど儲かるようになっているが、イギリスのGP制度では医師は患者を診ても診なくても報酬は変わらないため、自分に割り当てられた患者が健康になってくれた方がありがたいことになり、予防医療的な効果も期待できると考えられている。1980年代、高齢化を前にして医療費が急増することが目に見えている中で、当時の厚生省がイギリスのGPに似た制度を導入しようとする理由は十分に理解できる。
ただし、日本の国民皆保険制度は健康保険証を持って行けば、日本中のどの医者にも自由に診てもらうことができるフリーアクセスが最大のウリになっている。しかし、家庭医制度は元々、家庭医が患者の医療へのアクセスにおけるある種のゲートキーパー的な機能を果たすことがその目的でもあるため、何はともあれ必ず決まった家庭医に診てもらわなければならない。これが、どの医者に診てもらえるかを自由に選べる現在の日本のフリーアクセスとは相容れない面があることは紛れもない事実だ。ただし、日本のフリーアクセスが、患者にとって本当の意味でどれほどの価値があるのか、またそれが実際に医療の質を保証してくれているのかなどについては、十二分に検証すべき論点と言えるだろう。
コロナの流行が始まる以前から、高齢化が進む中での高齢者に対する医療体制の整備や、生活習慣病が蔓延する中での予防医療の重要性などの観点から、家庭医のニーズは高まっていた。また、それがないことによる医療費の野放図な膨脹も、大きな問題になっていた。しかし、コロナの流行が始まってから、日本の医療はいよいよその脆弱性を完全に露呈させてしまった。今や言い古された台詞になっているが、人口あたり世界最大の病床数を誇る日本が、欧米の数十分の1から数百分の1の感染者数で医療崩壊の危機を迎えている原因は、未知の感染症に対する備えが不十分だったことと同時に、イギリスのGPやアメリカのファミリードクターのような一般市民が何でも相談できる家庭医が不在だったことも、かなり大きなウエイトを占めているのではないか。コロナ対策でも入り口と出口のところで患者のこれまでの病歴や家庭環境などを熟知した家庭医がいるといないとでは、その対応はまったく違ったものになっていたと考えられるからだ。
国会で、現役の医師で衆院議員の中島克仁氏(立憲民主党)から家庭医制度の導入の如何を問われた田村憲久厚労大臣は、「かかりつけ医は充実させていきたいが、イギリスのGPのような現在のフリーアクセスを制限することになるゲートキーパー的な制度には抵抗が強い」といった趣旨の答弁をしている。国民皆保険制度は国民の大多数が支持するものだが、それがイコール・フリーアクセスなのかどうかは更なる議論が必要だろう。眼科や内科の専門医と同じように厳しい基準で総合診療医として認定された「家庭医」を持つことができることの安心感やメリットは決して小さくない。いきなりイギリスのようにNHSにそのまま行かずとも、国民皆保険制度を維持しつつ、ワンストップの家庭医を持てるような制度の構築は、今からでも十分に検討に値するのではないか。
今週は過去30余年にわたり医療問題を追いかけてきたジャーナリストでビデオニュース・ドットコムの迫田朋子氏とともに、家庭医とはどのような制度で、患者にとってどのようなメリットがあり、なぜ医師会がこれに執拗に抵抗するのかなどについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。


