原理原則なき「デジタル改革関連法」では個人情報は護れない 
NPO法人情報公開クリアリングハウス理事長
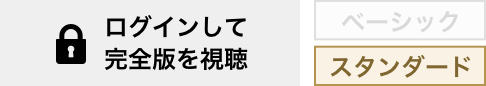



1972年東京都生まれ。96年横浜市立大卒。同年「情報公開法を求める市民運動」事務局スタッフ。99年NPO法人情報公開クリアリングハウスを設立、室長に就任。理事を経て2011年より現職。共著に『社会の「見える化」をどう実現するか―福島第一原発事故を教訓に』、『情報公開と憲法 知る権利はどう使う』など。
安倍政権の検証をシリーズで行ってきたが、恐らくその中でも今回こそが一番重要なテーマだと言っても過言ではないだろう。なぜならば、他のすべての問題が今回のテーマに依存しているからだ。
安倍首相は辞任を表明した2020年8月28日の会見で、歴代最長となった自らの政権のレガシーを問われ、「歴史の検証に委ねたい」と語った。しかし、政権の実績を評価するためには、正確な記録が残され、それが公開されていることが大前提となることは言うまでもない。
長年、公文書の情報公開に取り組んできたNPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、そもそも日本では政権の意思決定過程を公文書として記録に残さなければならないという概念自体が希薄なところにもってきて、安倍政権以降の官邸一強体制の下で、内閣人事局などで一元管理されるようになった幹部官僚たちが政権に忖度するようになったため、後に政治家、とりわけ官邸にとって不都合になる可能性がありそうな公文書はなるべく残さないようにしようという雰囲気が益々強くなってしまったと指摘する。特に、森友学園事件などで交渉記録や決裁記録を詳細に残していたことがかえって徒となり、遂には改竄事件にまで発展してしまったことで、官僚たちの間でそういう事態に追い込まれることはあらかじめ避けておきたいと考える心理が働くようになってしまったという。
加計学園問題では総理を始めとする政府の高官がいつ誰と会ったかを記録した面会記録が1日で廃棄されていたり、首相や官房長官の日程が記者会見や国会出席など1日あたり3~4件しか書き込まれていないものしか公文書としては残されていないという衝撃的な事実も明らかになった。アメリカでホワイトハウスの入退出記録が詳細に記録されていたり、大統領や政府高官の日程がニクソン大統領の時代から詳細に公文書に記録されているのと比較すると、日本の公文書管理と情報公開は50年以上も世界から後れを取っていると言わざるを得ない状況だ。いや、日本の場合、1999年の情報公開法の施行から、ここに来てむしろ状況が後退している面すらある。
政府の意思決定過程を記録した議事録にしても、政府要人の面会記録にしても、それを公文書として記録に残しておくことで、短期的には現在権力の座にある人たちが利益相反が疑われる関係を持っていたり、権力の濫用がないかをチェックすることが可能になる。民主主義を正常に機能させる上で、これはとても重要な機能だ。しかし、同時に、安倍前首相の言葉を借りるまでもなく、公文書は長期的には、政府の実績を歴史の検証に委ねることを可能にする唯一の手段という意味でも重要な意味を持つ。もし政府が後に悲劇的な結果を生む間違いを起こしていたとすれば、どこでその間違いが始まったのかを検証することで、同じ過ちを繰り返さないようにすることも可能になろうが、そのためには意思決定過程が詳細に記録されていることが必須となる。
安全保障上の理由やプライバシー、刑事捜査に絡む情報など、もしそれが今、公開されれば国益が損なわれるような情報なのであれば、何でもかんでも今すぐに全てを公開しろとまでは言わない。しかし、それでも公文書としてきちんと記録に残した上で、情報公開法の基準に則り一定期間、部分的、あるいは全体を非公開にするという手段もある。しかし、今の日本の政府が記録を残したくない、あるいは残そうとしない理由は残念ながら、そんな崇高な次元の話ではないように見える。それは単に、その役所や官僚自身にとって不都合なものだったり、特に安倍政権以降は、政権にとって不都合だからだったり、記録に残しても恥ずかしくないような十分な根拠や合理性、正当性のない恣意的な意思決定が至る所でなされているからというのが実情なのではないか。
そんな恥ずかしい記録を残したところで、どの道、歴史の検証には耐えられないではないかという声も聞こえてきそうだが、それは話が本末転倒だ。そもそも必ず記録に残され、いずれは公開されるということになれば人間、極端に恥ずかしいことはできなくなる。少なくとも、認可に際して首相の友人の会社を優遇したり、首相の妻が乗り気だからという理由で国有地を極端に安く払い下げたり、首相が国会で啖呵を切ってしまったのでそれに合わせて決裁文書を改竄したり、政府が主催する会合に首相の後援会を丸ごと招待させたり、政府の施策に反対した学者が学術会議のメンバーになることを拒否したりはできなくなるはずだ。日本でいまだにそういうことが平気でできてしまうのは、意思決定過程を記録に残さなくてもいいという大前提があるからではないか。これは、もし意思決定過程がきちんと記録されていれば、仮にそういうことがなかった場合も、それが容易に証明ができたことを意味している。
アメリカのトランプ大統領はあからさまに身贔屓をしたり、自身の個人的な好みで役人の任免を行うことで多くの批判を招いているが、彼は問われればその理由を隠さない。しかし、日本では恣意性が疑われる意思決定が行われ、それが問題になった時、政治家は記者会見でも国会でも、まるですっとぼけた答弁しかしない。身代わりに差し出された実務の責任者や関係者を国会に証人喚問までしても、本当に何が起きたのか、またなぜそれが起きたのかなどは最後まで明らかにならない。もちろん意思決定過程は公文書として記録されていないし、仮に一方の関係者が証言をしても、面会記録などが残っていないため、裏付けが取れないまま有耶無耶に終わってしまう。これでどうやって政権の成果を歴史の検証に委ねようというのだろうか。
課題は山積しているが、何をおいてもまず公文書管理と情報公開の後進国から卒業しなければ、日本の民主主義は「任せておいてブーたれる」だけの「おまかせ民主主義」から一向に脱皮することができない。その卒業のために一丁目一番地となるのが公文書管理と情報公開だ。現行の公文書管理法と情報公開法は不備も多いが、少なくともその精神を徹底し法律を順守するところから始める必要がある。ところが官僚教育の中で、公文書管理や情報公開の重要性を真剣に教えているという話は終ぞ聞かない。まさか未だに論語の「知らしむべからず由らしむべし」を地で行こうと考えているわけでもあるまいに。ちなみに上記の言葉は「民は知らせる必要はなく、ただ従わせればいい」などという為政者にとって都合のいい誤訳が横行しているようだが、その真意は「民を為政者に従わせることはできるが、その理由を理解させることは難しい」だ。つまり「だからこそ、民に対しては丁寧な説明を尽くしなさい」という教訓を込めた言葉なので、為政者の方々はくれぐれもお間違いのないように願いたい。
安倍政権下で明らかになった公文書管理と情報公開の問題点と今後の課題などについて、同分野の一人者で数々の情報公開請求訴訟を今も続けている三木由希子氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。