現行の成年後見制度では認知症になった人の権利を守れない 
弁護士、全国権利擁護支援ネットワーク顧問
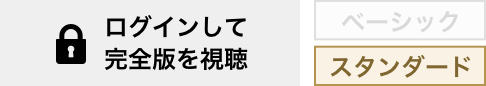



1953年福岡県生まれ。76年立命館大学法学部卒業。82年同大学大学院法学研究科博士後期課程修了。2000年9月弁護士登録。佐藤彰一法律事務所(現PAC法律事務所)を設立し代表に就任。立教大学教授、法政大学教授を経て、12年より現職。全国権利擁護支援ネットワーク代表を兼務。編著に『権利擁護がわかる意思決定支援』。
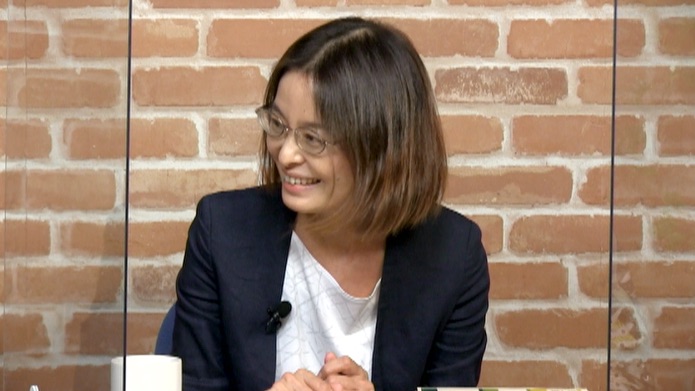
今年8月、一つのデータが大きな衝撃を与えた。認知症のひとが保有する金融資産が現時点で143兆円にのぼるという試算結果を、民間のシンクタンクが発表したのだ。
現在、認知症患者は500万人をこえ、軽度認知障害を合わせるとすでに1000万のオーダーになっているといわれている。認知症になり本人が判断できなくなると、親族であっても他者が預金を引き出すことは難しくなる。一方で判断が難しくなった高齢者をねらった振り込め詐欺の被害は増え続けており、高齢者の金融資産を守ることはますます重要になっている。
こうしたことの解決策として考えられているのが成年後見制度で、2年前には議員立法として成年後見制度利用促進法が成立している。しかし、この制度が使いにくく費用もかかることから、利用した人たちからは批判の声があがっている。全国権利擁護支援ネットワーク代表で国学院大学法学部教授の佐藤彰一氏は、成年後見制度自体が制度疲労をおこしており、現状のままでは問題が大きいと指摘する。
そもそも成年後見制度は、2000年に介護保険がスタートした際に、介護サービスの利用がそれまでの行政による措置から、本人との契約となることを受けて、判断能力が不十分な高齢者に対する施策として成立したものだった。しかし、後見人の選任等に家庭裁判所の判断が必要となるなど、当初から金融資産を守ることに重点が置かれた「重い制度」であり、これを本人のためにどう活用するかという視点は薄かったと、佐藤氏はいう。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でないとされる場合、権利擁護の観点から、以前は、第三者が代行決定するものと考えられてきたが、今は本人の意思決定支援を重要すべきという考えに変わってきている。本人に判断能力があるかどうかを他者が決めることができないという前提のもと、「能力がないと推定」するのではなく、「能力があると推定」して、そのひとの意思決定支援をするというパラダイム転換が求められていると、佐藤氏は主張する。
権利擁護の仕組みをどう整えてゆくべきか、まずは生活支援の視点が重要であると述べる佐藤彰一氏にジャーナリストの迫田朋子が聞いた。