航空機の重大事故を防ぐために設けられた幾重ものセーフティーネットはなぜ働かなかったのか 
元航空管制官
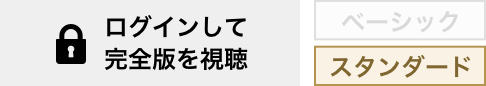


| 完全版視聴期間 |
(期限はありません) |
|---|

1946年愛知県生まれ。69年慶應義塾大学法学部卒業。同年、日本航空に入社。DC-8、ボーイング747、エンブラエルE170などに乗務。2011年退役。著書に『747 ジャンボ物語』、『乗ってはいけない航空会社』など。

新年早々、北陸地方が大地震に見舞われた翌日、今度は東京の羽田空港であり得ないような大事故が起きた。
着陸直後の日本航空の旅客機が滑走路上で海上保安庁の航空機とハイスピードで衝突し、大破した海保機ボンバルディア300に搭乗していた6人のうち5人が死亡するという、何とも痛ましい事故だった。
日航機も衝突後炎上し機体全体が炎に包まれたが、379人の乗客と乗員は脱出シューターを使って緊急脱出を図り、奇跡的に1人の死者も出さなかった。ただし脱出に際して、14人の乗客が怪我をした。
空港の滑走路上で離陸許可を待つ小型機に、着陸してきた別の大型機が突っ込むという、あってはならない事故だった。
事故原因については現在運輸安全委員会が調査を行っているほか、警視庁も刑事捜査に乗り出しているので、その結果を待つしかない。しかし、そもそも警察の捜査は事故原因を究明することが目的ではなく、事故の刑事責任を誰に負わせるべきかを見極めるためのものだ。また、運輸安全委員会の調査は結論が出るまでに通常1年半から2年はかかる。その間も飛行機の運航は行われるし、事故が起きた羽田空港のC滑走路も運用を再開している以上、調査結果を待つことなく、改善されるべき点を洗い出す必要があるだろう。
ビデオニュース・ドットコムでは、元日本航空のベテランパイロットで2011年の退役後は航空評論家として活動している杉江弘氏に、なぜあのような悲惨な事故が起きたのかを聞いた。
航空行政を管轄する国土交通省では、事故の1週間後の1月9日に、管制官による管理体勢の強化や管制用語のパイロットへの周知徹底などの緊急対策を打ち出しているが、杉江氏はそうした対策は弥縫策に過ぎず、より本質的な改善が必要だと指摘している。
9日に出された国交省の緊急対策は、海保機の機長の側に管制からの指示の誤認があった可能性が高いとの指摘を受けたものだが、そもそもコミュニケーション・ミスや勘違いはいつ、どこで、誰に起きてもおかしくはない。むしろ、そのような誤認が起きた時に、それが大きな事故につながらないための安全策が十分に採られているかどうかが問われる。
まず杉江氏は羽田空港の過密状況を問題視する。羽田は東京オリンピックへの対応で国際線の離発着枠を大幅に増やしたために、今やアトランタ、ドバイに次いで世界で3番目に過密な空港になっている。五輪が終わった今、羽田の離発着便の一部を成田に戻すべきだと杉江氏はいう。
また、今回事故のあった羽田のC滑走路は、離陸と着陸の両方に使われており、それが離陸しようとする海保機と着陸したJAL機の衝突につながった。杉江氏は、世界には1つの滑走路で離発着の両方を兼ねるところは他にもあるというが、羽田より過密なアトランタやドバイの空港の滑走路はいずれも離陸と着陸はそれぞれが専用に運用されている。
また、今回海保機が管制からの指示を誤認し滑走路に出て40秒間停止していたことがわかっているが、管制のレーダーには本来出てはならない航空機が滑走路に出た場合、危険を伝えるために海保機が赤色で表示されていたはずだった。しかし、管制官は常時レーダーを見ているわけではないためこれに気づかず、JAL機の着陸許可を継続してしまった。管制官の人員不足などの問題が指摘されているが、特にC滑走路の担当管制官は離陸機と着陸機の両方を同時に監視しなければならず、更に負担が大きくなる。ちなみに羽田では北風運用の際はA滑走路が着陸専用、D滑走路が着陸専用に使われるが、今回事故のあったC滑走路だけは離発着の両方に使われている。
杉江氏は、常にレーダーを見ているわけではない管制官に危険を伝えるためには、危険な状況下ではレーダー内に機影を赤く表示するだけではなく、同時に音で危険を知らせる仕組みが必要だという。
また、許可を得ていない海保機が滑走路に進入した場合、ストップバーライトと呼ばれる赤い警告灯が滑走路の入り口のところに備え付けられていて、それが点灯することで危険を海保機のパイロットに伝える仕組みがある。しかし、羽田C滑走路のストップバーライトは現在工事中で、使われていなかった。また、そもそもストップバーライトは天候不良などで視程が600メートル以下の時しか使われておらず、視程が5,000メートルあったこの日は仮に工事中でなかったとしても利用されていなかったという。
杉江氏は視程の長短にかかわらず、ストップバーライトは常時運用されるべきだと語る。
また、杉江氏は自身のパイロット時代の経験から、仮に管制がレーダー上の危険を見落としていたとしても、最後には着陸準備に入ったJAL機側が、滑走路上で待機する海保機の存在を目視し、ゴーアラウンド(着陸復行)できなければならなかったと語る。航空機は地上15メートルからでも急遽ゴーアラウンドすることが可能だという。この日JAL機では副操縦士の社内審査に向けた訓練も兼ねていたため、後部座席には副操縦士の業務を確認するために教官が座っていた。コックピットには通常より1人多い3人のパイロットがいたことになる。その3人のうち誰一人として、着陸先の滑走路で主翼の右先端に青の、左先端に赤の航行灯を点滅させながら待機している海保機の存在に気づかなかったのはなぜなのか。
杉江氏によると、着陸しようとする航空機の滑走路に、離陸前の航空機や着陸した後なぜか動きが遅い航空機が止まっていて、直前でゴーアラウンドしなければならないようなことは、杉江氏自身も何度となく経験したことがあるという。今回の事故では海保機の誤進入も問題だが、管制からの指示を含め、なぜJAL機がそれを避けることができなかったのかということにも、大きな問題があったと杉江氏は言うのだ。
さらに杉江氏は、緊急脱出の仕組みにも問題があったと指摘する。今回JAL機が客室乗務員の機転もあり、シューターを使って全員を無事脱出させたことはよかったが、その一方で14人の怪我人が出たことを杉江氏は問題視する。怪我をした14人全員がシューターの使用時に負傷したのかは分かっていないが、杉江氏によると航空機のシューターは先端部で地面との間に段差があり、訓練を受けていない乗客が利用した場合、うまく足で着地して立ち上がれる人もいるが、多くの人が勢い余ってお尻から着地してしまい、お尻や腰を強く打ち付けてしまう場合があるのだという。特に高齢者の場合、骨折などの大怪我につながる危険性があり、杉江氏は以前からこの段差を解消するようにシューターの改善を提言しているが、一向に顧みられていないという。ちなみに、杉江氏によると、パイロットやキャビンアテンダントがシューターを使った脱出の訓練を行う場合、安全のためにシューターの先端部分の下にマットレスを敷いているそうだ。
また、日本の遅れた刑事司法制度も事故の原因究明の足枷になっていると杉江氏は言う。これは何十年も前から指摘されていることだが、日本では航空機や他の乗り物事故が起きた際、警察が刑事捜査を行うのが慣例になっている。しかし、これは日本も批准している国際民間航空条約(ICAO)のANEX13条項に明らかに違反している。大規模事故が起きた場合、飲酒や意図的な危険運転などよほどの重過失が認められない限り、個人の刑事責任を問うよりも、関係者を免責した上で、事故原因の究明や再発防止のために全面的に協力をさせることの方が、より公益的なメリットが大きいし、それが欧米や韓国などでは既に慣例化している。しかし、日本のようにあくまで警察が刑事責任を追求するのであれば、自身が刑事責任を問われる危険性がある関係者は、一様に事故調査に積極的に協力することが難しくなる。また、国土交通省の事故調査に全面協力した結果、そこに提供した証言や証拠が後に警察によって刑事捜査に使われる恐れもあるため、行政機関の事故調査にもうかうか協力していられない。この悪しき慣例が事故原因の究明を妨げているという事例は枚挙に暇がない。そろそろこのあたりも国際基準に合わせていく必要があるだろう。
元パイロットの杉江氏に、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。