これでは取り調べの可視化が進むわけがない 
映画監督
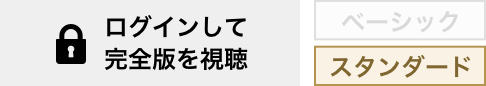


| 完全版視聴期間 |
(期限はありません) |
|---|

相次ぐ検察の不祥事や冤罪事件を受け、刑事司法制度の改革を議論してきた法制審議会の特別部会の委員で映画監督の周防正行氏が、7月11日、ビデオニュース・ドットコムのインタビューに応じ、9日に合意された最終答申案で取り調べの可視化が全刑事事件の2%にしか適用されないことが決まったことに大きな不満を覚える一方で、僅かでも取り調べの全過程の可視化の方向に向かったことについては今後につながるものとして評価したいとの思いを語った。
3年間の特別部会での議論を振り返り周防氏は、「自分たちの言葉がなかなか届かなかった」と、可視化を進めるべきだとする周防氏ら「非法律家」の意見が、警察・検察や裁判所などの法曹関係者が多数を占める会議では十分に尊重されなかったことに、悔しさをにじませた。
映画「それでもボクはやってない」で監督として痴漢冤罪事件を描いた周防氏は、元々この特別部会を、大阪地検特捜部による証拠改ざん事件や相次ぐ冤罪事件などを受けて、冤罪を出さないための制度改革を議論するために設置されたものと考えて、委員に就任したという。ところが、会議の名称が、「新時代の刑事司法制度特別部会」とされ、可視化については警察・検察の利害を代弁する委員たちから激しい抵抗を受ける一方で、盗聴権限の拡大や司法取引の導入など、警察・検察の権限の拡大が議題に含まれていることを知り、「前提が共有されていないことに途中から気づいた。実際には最初から捜査当局の権限拡大を図るための会議だったのだと思う」として、会議そのものの性格が、当初周防氏らが想定していたものとは違っていたことを指摘した。
そして、何よりも大前提が共有されていなかった点は、「警察・検察関係者たちは自分たちがこれまでやってきたことが間違っていたとは考えていなかった」ことだった周防氏は言う。「彼らの自分たちこそがこれまで日本の治安を守ってきたとの思いはものすごく強いものがあった。」
しかし、その上で、最終的に取り調べが録音・録画の対象となる事件が全刑事事件の2%に過ぎない裁判員裁判対象事件に限られたことについて周防氏は、「僅か2%といっても、これまで密室の取り調べでいかに自白を引き出すかしか考えてこなかった警察関係者にとって、これは絶望的に恐怖なことなんだと思う」として、この2%をきっかけにして警察の捜査のあり方が今後大きく変わってくる可能性に期待をにじませた。
とは言え、会議を通じてより根本的な問題が見えてきたことも周防氏は指摘する。3年間の議論を経て周防氏は、警察・検察の間で近代司法の要諦である「推定無罪の原則」は必ずしも重視されてないとの印象を持ったと語る。「彼らは現在の日本の治安を守っていけるのであれば、1人や2人の冤罪くらいはやむを得ないと考えているのだと思う。そして、一般の国民の中にもそう考えている人は多いのではないか。」周防氏はこのように述べ、なぜ推定無罪が重要なのかを教育や報道を通じて社会に訴えていくことの重要性を強調した。