自民党大敗の原因となった政治と金に対する有権者の不信感が一向に収まらないこれだけの理由 
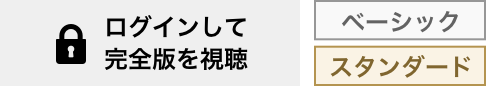

.jpg)
学校で起こるいじめを苦に自死する子どもが、残念ながら後を絶たない。
いじめをめぐっては、いじめの発生を学校ぐるみで隠ぺいしたり、学校がいじめと自死の関係を頑なに認めないなど、当事者やその家族にとってはつらい事態が相次いで起きていることは周知の事実だ。中には学校がいじめを認知していながら適切な対応を取っていなかったり、教員がいじめに加担しているケースなど悪質なものもあるが、その事実が家族にさえ十分に提供されない場合もある。
いじめを原因とする自死事件をきっかけにいじめが社会問題として認知された1985年以降、いじめ対策は制度的には進んできたが、いじめの認知件数は年々増加し、2022年度には681,948件にものぼっている。
このような危機的な状況を受けて、2013年にはいじめ防止推進法が制定され、重大事態と認知されたいじめについては調査報告が法律で義務づけられた。しかし、逆にそのことで調査報告書や調査過程の情報の公開が以前より問題になる事例が増えている。また、いじめを認知した際に学校から教育委員会に出される報告文書の情報公開も、いじめの加害者、被害者双方の個人情報などが多く含まれているため、被害者やその家族の希望とは裏腹に、どこまで情報公開ができるかについては未だに明確な基準が定まっていない状況だ。
いじめの調査報告に関する情報公開は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に定められてはいる。しかし、ガイドラインでは「情報公開条例の不開示事由を踏まえて適切に行うこと」とされ、無条件の公開を義務づけているわけではないため、その不開示事由の適用範囲が常に問題になる。しかも、被害者本人が死亡している場合、家族であっても個人情報保護法の壁が立ちはだかる。法定代理人は本人が生きている間は有効だが、死亡した場合は、家族でも他人と同じ扱いになるからだ。家族にも満足な情報が開示されない一方で、調査報告の公開については、「当事者家族の意向」を理由に幅広く黒塗りされたものしか出てこない場合が多く、実際はそれが当事者家族側の意向とは異なる対応だったことが後になって判明する場合も多い。
確かに子どものいじめ問題は情報公開上デリケートな側面があることは間違いない。しかし、それを理由に行政や教育委員会、ひいては学校による隠ぺいや責任逃れを許してはならない。本人や家族の無念を晴らすためにも、また社会として問題の所在を共有するためにも、適切な情報公開は必要だ。
いじめ問題の情報公開について、具体的な事例を参照しながら、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。