SNS選挙に踊らされないために 
横浜商科大学商学部教授
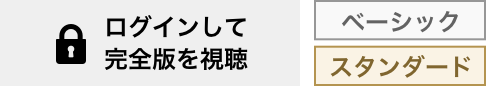



1963年宮城県生まれ。1986年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。同大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。フリーの評論活動を経て、2008年より現職。専門は政治思想史。著書に『未完のファシズム』、『近代日本の右翼思想』、『ゴジラと日の丸』など。

約70年前、当時5倍以上の経済規模を持つ超大国のアメリカとの無謀な戦争に突入した日本。なぜ日本が勝算もないまま必ずしもその目的さえ明らかとは言えないような無謀な戦争に突入したかについては、その後幾多の検証がなされている。しかし、仮にその「なぜ」が解き明かされたとしても、次はそうならないという保証はどこにもない。
政治思想史が専門の片山杜秀氏(慶応大学法学部准教授)は、今からほぼ100年前の1914年に開戦した第一次世界大戦に、その後の日本の暴走を解くカギがあると主張する。
ヨーロッパで始まった第一次世界大戦はアジアにも飛び火し、日本は東アジアにおけるドイツの拠点を攻め落とし、戦勝国となった。しかし、その10年前の日露戦争で、国力に圧倒的に勝るロシアを相手に、夥しい犠牲を出しながらも白兵戦で勝利した。日本にとって第一次世界大戦は、もはやこれからの戦争が白兵戦や精神力の戦いの時代ではなくなっていることを痛感させるに十分だった。つまり、歩兵に代わって航空機や戦車などの新しい兵器が主役を務めることになるこれからの戦争では、長期化する全面戦争を継続するだけの経済力や工業力、そして生産力の如何が勝敗を決める決定的な要素となっていた。命知らずの勇敢な歩兵の精神力だけで戦争に勝てる時代は終わったことを、連合軍の一員として欧州戦線をリアルタイムで視察した日本軍の幹部たちは認めざるを得なかった。
問題は「持たざる国」が「持てる国」に勝つことがもはや難しいことはわかったが、肝心の日本が「持たざる国」だったことだ。
片山氏は第一次大戦後の日本の軍部に多大な影響を及ぼした小畑敏四郎、石原莞爾、中柴末純などの軍指導者たちは、いずれも「持たざる国」が「持てる国」に勝てないことを熟知していたと説く。しかし、にもかかわらずなぜ「持たざる国」の日本は、世界で最も「持てる国」のアメリカとの全面戦争などという愚かな選択をしたのか。
片山氏は日本の政治機構に決定的な問題があったとの見方を示す。例えば、第一次大戦を視察して物量の重要さを熟知した小畑らは、日本は大国との全面戦争に勝ち目はないことを悟り、あくまで劣弱な相手との限定戦争のみを選択する政策を主張した。小畑らが主張した殲滅戦論というのは、おおっぴらにそうは謳っていないものの、実はあくまで劣弱な相手を想定したものに過ぎなかった。これからの戦争は「持たざる国」が「持てる国」とまともに戦っても勝てるはずがない。だから、相手を選び限定的な戦争に殲滅作戦で臨むことで有利な和平交渉に持ち込む。これが小畑らの殲滅戦思想の隠された要諦、つまり密教の部分だったと片山氏は指摘する。
しかし、日本では軍が政治に関与する度合いは強く制限されていた。そのため軍のこうした知識や認識が政治と共有されることは終ぞなかった。また、軍内部の権力闘争の結果、皇道派の小畑らは統制派に敗れ実権を失ってしまう。その結果、殲滅戦論の密教部分を除いた、ベタの殲滅戦思想のみが統制派によって踏襲されていったと片山氏は言う。
関東軍の参謀だった石原莞爾らが主導した満州国の建国及びその属国化も、元はといえば「持たざる国」の日本を「持てる国」にするための手段として選択された政策だったと片山氏は言う。石原らは、満州の開発などを通じて日本経済が順調に成長していけば、1970年頃までには日本もアメリカ並の経済力を身につけることが可能になると考え、その頃に日米の最終戦争を想定したという。しかし、言うまでもないが満州への侵攻は国際社会、とりわけソ連との緊張を高め、日本は石原が想定したよりも30年近くも早く日米開戦に突入してしまう。
『戦陣訓』の著者の一人とされる中柴末純にいたっては、これからの戦争では物量かカギであることを知れば知るほど、そして日本に勝ち目がないことを知れば知るほど、より精神論に傾斜していくという逆説的な動きを見せた。その結果が「生きて虜囚の辱めを受けず」であり、玉砕の美化だった。
どうもこうして見ていくと、日本が無謀な戦争に突入していった際、少なくとも軍部には、第一次大戦の教訓として「持たざる国」は「持てる国」には勝てないという認識や分析が十分過ぎるほど共有されていたようだ。しかし、その時の日本はその分析を全くといっていいほど政治に活かすことができなかった。活かせなかったばかりか、むしろそれとは正反対の政治行動を取っている。
それはなぜなのか。片山氏は日本の政治機構のあり方に決定的な特徴、いや欠陥と言うべきかもしれない問題があり、とかく日本人は権力の集中を嫌がる傾向があるのだと言う。普段は権力が分散しているため、なかなか意思決定ができない。誰か強いリーダーが出てくると、先を争うようにそのリーダーの足を引っ張り始める。そのため内輪もめが絶えない。だから政策の継続性を保つことも難しいし、誰が主導するともないままに間違った政策が選択され、それがそのまま実行に移されることも多い。
日米開戦時に陸軍大将の東条英機が首相と陸軍大臣と参謀総長を兼任したことが、軍部専政の証のように言われることがあるが、片山氏は逆にこのことが、日本の政治制度が戦争という有事にあっても分散した権力がお互いを牽制し合うようになっていたことの証左であると指摘する。
この一連のエピソードを現在の政治状況に当てはめると、何が見えてくるだろうか。エネルギー資源を「持たざる国」の日本が、明らかに地理的条件の不向きな原発を維持・推進しようとしてきた。そして、あれだけの事故を目の当たりにしながら、「ああでもないこうでもない」論争が続く。政府は当初、夏中に決定する予定だった次代のエネルギー政策の策定を、年末まで延ばす方針だと言う。原発を継続できれば経済大国としての地位が維持できる。「持たざる国」を何とかして「持てる国」に変えていこうとする試みという意味では、これは石原莞爾的なアプローチということになるのだろうか。しかし、石原莞爾は満州の資源開発によって日本を「持てる国」にした先に、「世界最終戦争」と法華経の説くユートピアの実現を夢見ていたという。
片山氏自身は「背伸びはやめて、静かに着地して静かに生きる」という選択肢を薦めるが、皆さんはどう思われるだろうか。
第一次世界大戦を基軸に据えた独自の視点で日本が太平洋戦争へ突き進んだ過程を分析してきた片山氏とともに、なぜ日本はダメだとわかっていることを繰り返しやってしまうのか、そして今日の日本が当時と変わった点、変わっていない点は何なのかなどを、哲学者の萱野稔人と社会学者の宮台真司が議論した。